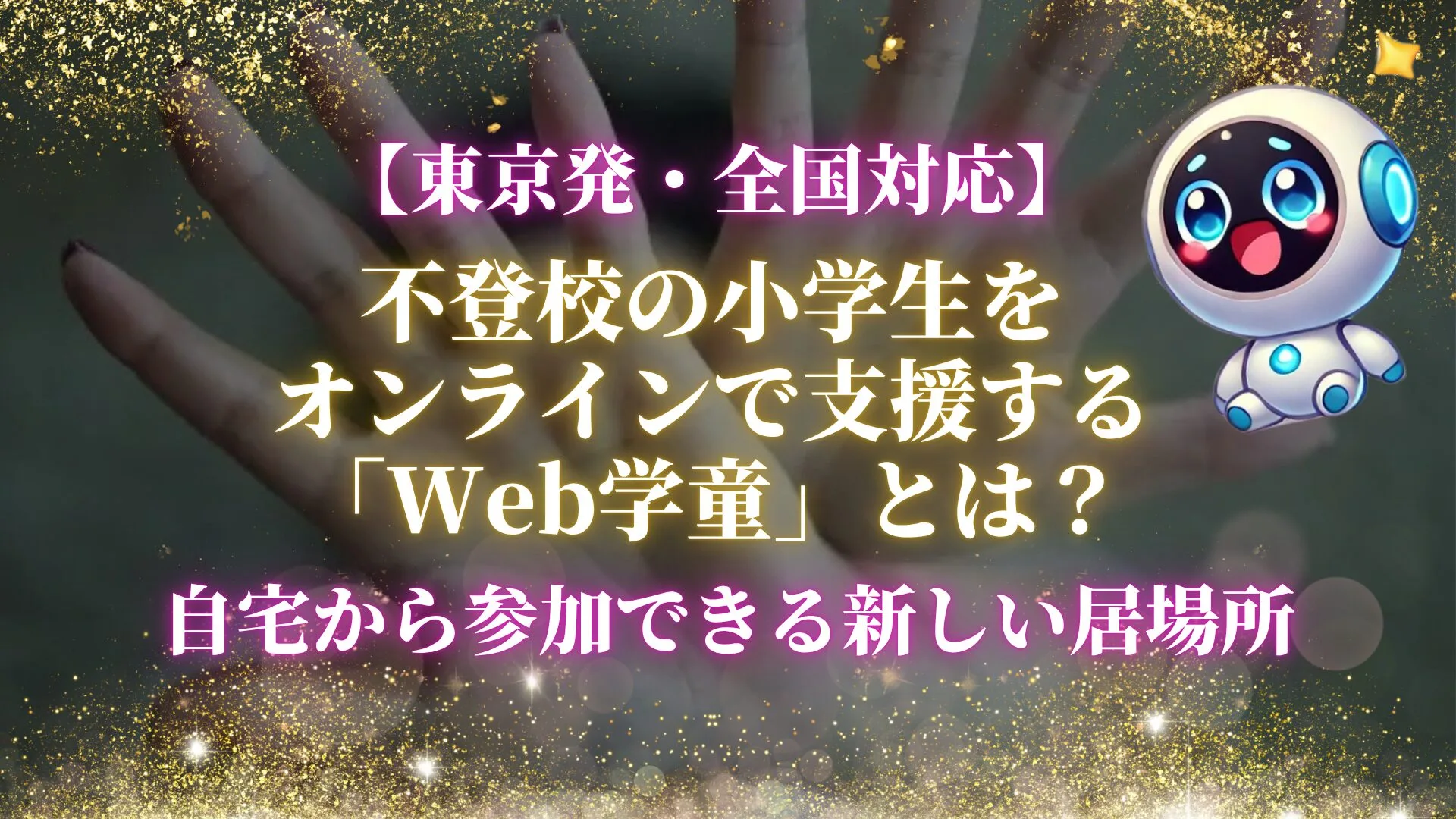不登校の小学生を持つ親御さんの悩みと「Web学童」という新しい選択肢
増加する小学生の不登校|2024年の最新データから見る現状
文部科学省「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、2023年度の小学生の不登校児童数は約10万5千人と過去最多を更新しました(※2025年6月現在の最新公表データ/参考元:https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_1_2.pdf)。
これは前年度比で約22%の増加となり、35人に1人の割合で不登校の状態にある計算になります。都市部を中心に全国的な増加傾向が見られ、各自治体でも対応が急務となっています。
しかし、数字だけでは見えてこない実態があります。「学校に行きたくても行けない」という子どもたちの苦しみ、そして「どうサポートすればいいのか分からない」という保護者の方々の悩み。北海道から福岡まで、全国各地で同じような思いを抱えている家庭が増えています。
このような状況の中、従来の支援方法に加えて、新たな選択肢として注目されているのが「オンライン学童」です。「Web学童」は、東京を拠点に全国の不登校児童とその家族を支援するサービスとして展開しています。自宅にいながら専門的な支援を受けられるという新しいアプローチは、地理的な制約を超えて、すべての子どもたちに支援の機会を提供することを目指しています。
「学校に行けない」だけじゃない、親が抱える3つの不安
不登校の子どもを持つ保護者の方々からは、次のような声がよく聞かれます。「朝になると『お腹が痛い』と言い出す我が子を見て、どう接すればいいか分からない」「仕事を休んで付き添うべきか、それとも一人で留守番させるべきか」──このような日々の選択に悩む方は少なくありません。
実際に保護者の方々が抱える不安は、大きく3つに分類されます。
1つ目は「学習の遅れ」です。学校に行けない期間が長くなるほど、同級生との学力差が開いていくのではないかという心配。
2つ目は「社会性の発達」への懸念です。友達と遊ぶ機会が減り、コミュニケーション能力が育たないのではないかという不安。
そして3つ目は「将来への影響」です。このまま不登校が続いたら、進学や就職にどう影響するのかという長期的な心配です。
名古屋市在住のCさん(40代)は「最初は『少し休めば学校に戻れる』と思っていました。でも3ヶ月が過ぎ、半年が過ぎても状況は変わらず、焦りばかりが募りました」と振り返ります(※個人の体験談です)。
このような経験を持つ保護者は全国に多くいらっしゃいます。Web学童は、こうした複合的な不安に対して、包括的なサポートを提供することで、親子双方の負担軽減を目指しています。
オンラインだからこそできる、Web学童の柔軟な支援アプローチ
従来の不登校支援では、「まず外に出ること」が第一歩とされることが多くありました。しかし、それ自体がハードルとなってしまう子どもも少なくありません。Web学童が採用するオンライン支援は、この「最初の一歩」を踏み出しやすくすることを意図しています。
自宅という安心できる環境から参加できることで、子どもたちは無理なく活動に加わることができます。パジャマのままでも、好きなぬいぐるみを抱えながらでも、まずは画面越しに「つながる」ことから始められるのです。実際に利用している東京都のDさん親子は「最初はカメラをオフにして音声だけの参加でしたが、3週間後にはフィルター越しではありますが顔を出して先生と話すようになりました」と変化を語ります(※体験談は個人の感想であり、効果を保証するものではありません)。
さらに、オンラインの特性として、全国各地の子どもたちとつながることが可能です。北海道の子と福岡の子が同じ活動に参加し、地域を超えた交流の機会を持つこともできます。また、専門スタッフも全国から配置できるため、質の高い支援の提供を目指しています。このような柔軟性を活かしたサポートを展開しています。
Web学童とは?従来の支援との違いを分かりやすく解説

家庭教師・フリースクール・通常の学童との比較表
不登校の子どもへの支援方法は様々あり、それぞれに特徴があります。以下、各サービスの特徴を整理してご紹介します。
家庭教師は主に学習面でのサポートに特化し、1対1の個別指導が特徴です。週に数回、1〜2時間程度の利用が一般的で、料金は1時間あたり3,000〜5,000円程度が相場です。学習指導には優れていますが、社会性の育成や心のケアまではカバーしにくい面があります。
フリースクールは、不登校の子どもたちが通える民間の教育施設です。東京や名古屋、大阪などの都市部を中心に増えていますが、地方では選択肢が限られることもあります。月謝は地域により異なりますが、東京都内では月額4〜8万円、地方では3〜5万円程度が一般的です。実際に通う必要があるため、交通費も別途かかります。また、定員があるため希望してもすぐに入れない場合もあります。(参考元:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tyousa/__icsFiles/afieldfile/2015/08/05/1360614_02.pdf)
Web学童は、オンラインでの包括的な支援が特徴です。学習支援に加えて、グループ活動による社会性の育成、専門スタッフによる心のケアまで提供します。好きな時間帯に利用可能で、月額制となっています。ただし、実際に会っての活動を希望する場合には適さない面もあります。
通常の学童保育は、学校に通っている子どもが放課後に利用する施設のため、不登校の子どもは利用対象外となります。
オンラインならではの3つのメリット|全国どこからでも参加可能
Web学童がオンラインで提供されることには、以下のようなメリットがあります。
1つ目は「アクセシビリティ」です。北海道の山間部でも、福岡の離島でも、インターネット環境があれば参加可能です。地理的な制約を受けずに支援を受けられることは、地方在住の方にとって大きな利点となります。
2つ目は「段階的な参加が可能」という点です。最初はカメラオフ・音声オフでの見学から始め、慣れてきたら音声だけ、さらに慣れたらカメラもオンにする──このように、子どものペースに合わせて少しずつ参加度を上げていくことができます。愛知県のFさん(小学3年生)は、最初の1ヶ月は画面を見ているだけでしたが、徐々に活動に参加するようになりました(※体験談は個人の感想です)。
3つ目は「保護者の負担軽減」です。送迎の必要がないため、仕事を続けながら子どもの支援を受けることができます。また、子どもの様子を自宅で見守れるため、安心感もあります。東京都で在宅勤務をしているGさんは「仕事の合間に子どもの様子を確認できるので、お互いに安心して過ごせています」と語ります(※個人の体験談です)。
Web学童で受けられる具体的な支援内容

学習支援|個別最適化されたオンライン学習プログラム
Web学童の学習支援は、一人ひとりの学習状況、興味関心、そして心の状態に合わせたプログラムを提供することを目指しています。例えば、算数が苦手で自信を失っている子には、理解できるレベルから丁寧に復習し、「できた!」という成功体験を積み重ねていくアプローチを取ります。
使用する教材は学校教材を中心に、ゲーミフィケーションを取り入れた学習アプリ、動画教材、そして必要に応じて紙のワークブックも併用します。大阪府のHさん(小学5年生)のお母様は「学校では集中できなかった息子が、オンラインの算数ゲームなら長時間取り組めるようになりました」と変化を語ります。
学習支援で重視しているのは「将来の選択肢を増やすこと」です。不登校になった子どもの中には、学習に対してネガティブな経験を持つケースも見られます。Web学童では、スモールステップで達成感を味わいながら、自分のペースで学習を進められる環境を提供します。さらに、プログラミングや英会話、オンライン体験など、学校の教科書にとらわれない幅広い学びの機会も用意しています。
心のケア|専門スタッフによる定期的な面談サポート
不登校の背景には、様々な心理的要因があることも少なくありません。Web学童では、臨床心理士や公認心理師などの専門資格を持つスタッフが、定期的に子どもたちの心のケアを行います。これは単なるカウンセリングではなく、日常的な関わりの中で自然に行われる支援を心がけています。
具体的には、朝の会での様子確認、活動中の観察、そして月に1回の個別面談を通じて、子どもの状態を把握します。福岡県のKさん(小学3年生)のケースでは、絵を描くことを通じて気持ちを表現する機会を設けました(※個人の体験談です)。
また、必要に応じて保護者との連携も行います。子どもの様子で気になることがあれば保護者に共有し、家庭でのサポート方法についても相談に応じます。東京都のLさんのお母様は「専門家に相談できる環境があることで、親としても安心できます」と話されています。
保護者支援|親御さん向けの相談窓口と情報共有
Web学童では、子どもだけでなく保護者の方々へのサポートも重視しています。不登校の子どもを持つ親御さんは、様々な悩みを抱えていることが多いため、それらに対応する体制を整えています。
月1回の「保護者面談」では、お子さんの様子を共有するとともに、ご家庭での困りごとについても相談できます。大阪府のMさんは「子どもへの接し方についてアドバイスをもらい、気持ちが楽になりました」と振り返ります。
料金体系と他サービスとの比較

Web学童の料金プラン|月額制から単発利用まで
Web学童の料金プランは、一般的に年間プランもしくは月額プランに応じて設定されています。
年間プラン
・月額:9,000〜円(税別)
・月間指導時間:約10時間
・利用時間:24時間
※注意事項:途中解約不可
月額プラン
・月額:23,000円(税別)
・頻度:週2回
・利用時間:24時間
これらの基本料金には、学習指導、グループ活動、保護者面談などが含まれております。追加料金が発生する場合は、特別イベントや個別教材などに限定されることが多いです。割引制度として、兄弟割引、紹介割引などを設けております。
【比較表】Web学童 vs 家庭教師 vs フリースクール|コストパフォーマンスを検証
各支援サービスの特徴と費用を比較すると、それぞれに長所と短所があることがわかります。
家庭教師(週2回、1回2時間の場合)
- 月額費用:3〜5万円程度
- 特徴:1対1の個別学習指導
- メリット:きめ細かな学習指導が可能
- デメリット:社会性の育成や心のケアは限定的
フリースクール
- 月額費用:東京都内4〜8万円、地方3〜5万円程度(別途交通費)
- 特徴:実際に通って活動する
- メリット:対面での交流が可能
- デメリット:地域により選択肢が限られる、通学が必要
Web学童
- 月額費用:9,000円〜23,000円(プランによる)
- 特徴:オンラインでの包括的支援
- メリット:学習・社会性・心のケアを総合的にサポート、全国どこからでも参加可能
- デメリット:対面での活動を希望する場合には不向き
それぞれのサービスには特徴があり、お子さんの状態や家庭の状況に応じて選択することが重要です。
自治体の補助金・支援制度の活用方法
不登校支援に関する経済的負担を軽減するため、各自治体で様々な支援制度が用意されています。ただし、制度内容は自治体により大きく異なり、変更される可能性もあるため、最新情報の確認が必要です。
一般的な申請の流れは以下の通りです:
- 市区町村の教育委員会や子育て支援課に相談
- 利用可能な制度の確認
- 必要書類の準備(状況説明書、収入証明書、サービス利用証明書など)
- 申請書の提出
- 審査・認定
北海道のRさんは「Web学童のスタッフに教えてもらい、自治体の補助制度を利用できるようになりました」と話します(※個人の体験談です)。
Web学童では、各地域の補助制度に関する情報提供も行っていますが、制度の詳細や最新情報については、必ず各自治体の窓口でご確認ください。
実際の利用者の声|Web学童で変わった親子の日常

【体験談1】東京都在住Aさん親子|3ヶ月で見えてきた変化
※以下は個人の体験談であり、効果を保証するものではありません。
東京都世田谷区在住のAさん(42歳)と息子のユウキくん(仮名・小学4年生)は、2025年1月からWeb学童を利用しています。ユウキくんは小学1年生の3学期から学校に行けなくなり、当初は一時的なものと考えていたそうです。
「朝になると体調不良を訴え、トイレから出てこない日々が続きました。医療機関でも相談しましたが、なかなか改善しませんでした」とAさんは当時を振り返ります。
Web学童の利用を始めて最初の1ヶ月は、画面の前に座ることから始まりました。カメラはオフの状態でしたが、スタッフの声かけと他の子どもたちの様子を見ているうちに、少しずつ変化が見られるようになりました。
3ヶ月目にはフィルター越しにで挨拶ができるようになり、Aさんは「息子の笑顔を見られるようになり、前進を感じています」と話してくれました。
【体験談2】地方在住Bさん親子|都市部と同じ支援を自宅で
※以下は個人の体験談であり、効果を保証するものではありません。
福岡県の山間部に住むBさん(38歳)と娘のサクラちゃん(仮名・小学5年生)のケースでは、地理的な制約が大きな課題でした。最寄りの支援施設まで車で1時間半かかる環境で、選択肢が限られていました。
「都市部なら様々な支援があるのに、私たちの地域では難しい。将来への不安で眠れない日々でした」とBさんは語ります。
オンラインでの支援に最初は不安もありましたが、無料相談を経て利用を開始。サクラちゃんは全国の同年代の子どもたちと交流できることに刺激を受けたようです。
6ヶ月後、サクラちゃんは地元の適応指導教室にも通えるようになりました。Bさんは「オンラインでの経験が、外に出る勇気につながったようです」と振り返ります。
よくある質問|利用開始前の不安を解消
Q1. うちの子はパソコンが苦手ですが、大丈夫でしょうか?
A. 操作方法は最初にスタッフが丁寧にサポートします。多くのお子さんが1週間程度で基本操作に慣れています。タブレットでの参加も可能です。
Q2. 他の子とトラブルになったりしませんか?
A. すべての活動にスタッフが同席し、適切にサポートします。万が一、相性が合わない場合は、グループの変更など柔軟に対応します。
Q3. 効果が感じられない場合、途中で辞められますか?
A. はい、月額プランの場合、1ヶ月単位でいつでも退会可能です。ただし、変化には個人差があり、3ヶ月程度継続することで変化が見られることが多いです。
Q4. 学校との連携はどうなっていますか?
A. 出席認定については各学校の判断によります。ご希望に応じて、Web学童での活動内容を学校に報告することは可能ですが、事前に在籍校との協議が必要です。
Q5. きょうだいで利用する場合の割引はありますか?
A. はい、ありますので詳細はお問い合わせください。
Web学童の始め方|無料相談から利用開始までの流れ

まずは無料相談|専門スタッフが丁寧にヒアリング
Web学童への第一歩は、無料相談から始まります。経験豊富な専門スタッフが60分間、じっくりとお話を伺います。相談は完全オンラインで、ご都合の良い時間に設定できます。
相談では、お子さんの現在の状況、不登校になった経緯、現在の生活リズム、興味関心、保護者の方が抱えている悩みなどをお聞きします。東京都のSさんは「スタッフの方が優しく聞いてくださり、安心して話すことができました」と振り返ります。
その上で、Web学童でどのようなサポートが可能か、プログラム内容、料金プランなどについて説明します。相談したからといって必ず申し込む必要はありません。
体験利用|実際の雰囲気を親子で確認
無料相談の後、興味を持っていただけた方には「無料体験」をご案内しています。実際のプログラムに参加することで、Web学童の雰囲気やお子さんとの相性を確認できます。
体験初日は、親子一緒に参加していただくことも可能です。大阪府のUさんは「最初は私も隣に座っていましたが、子どもが慣れてきて一人で参加するようになりました」と体験を語ります(※個人の体験談です)。
体験期間中は、担当スタッフがお子さんの様子を観察し、最終日にフィードバックを行います。お子さんの特性や可能性について、客観的な視点からお伝えします。
本格利用開始|お子さんのペースに合わせた段階的な参加
無料体験を経て本格的にスタートする際も、お子さんの状態に合わせて段階的に進めます。最初は短時間から始め、徐々に参加時間を延ばしていくことが一般的です。
利用開始時には、お子さん専用の「個別支援計画」を作成します。これは、お子さんの特性、目標、今後の見通しなどをまとめたものです。
保護者の方へのサポートも本格的にスタートします。活動報告、定期面談、LINE相談窓口など、不安や疑問をいつでも相談できる体制を整えています。北海道のXさんは「困ったときにすぐ相談できる環境があって心強かったです」と振り返ります。
不登校からの回復は一直線ではありません。良い日もあれば、そうでない日もあります。Web学童では、そんな波も含めてお子さんの成長を見守り、サポートを続けます。
今こそ、新しい一歩を踏み出しませんか?
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。不登校という状況は、お子さんにとっても、保護者の方にとっても、本当に辛く苦しいものです。でも、決して一人で抱え込む必要はありません。
まずは無料相談から始めてみませんか?専門スタッフが、あなたの話をじっくりと伺います。また、より詳しい情報をお求めの方は、資料請求も承っております。
もし、この記事を読んで少しでも「話を聞いてみたい」「うちの子にも合うかもしれない」と感じていただけたなら、ぜひその小さな一歩を踏み出してみてください。その一歩が、お子様とあなたの明日を、より明るいものに変えるきっかけになるかもしれません。