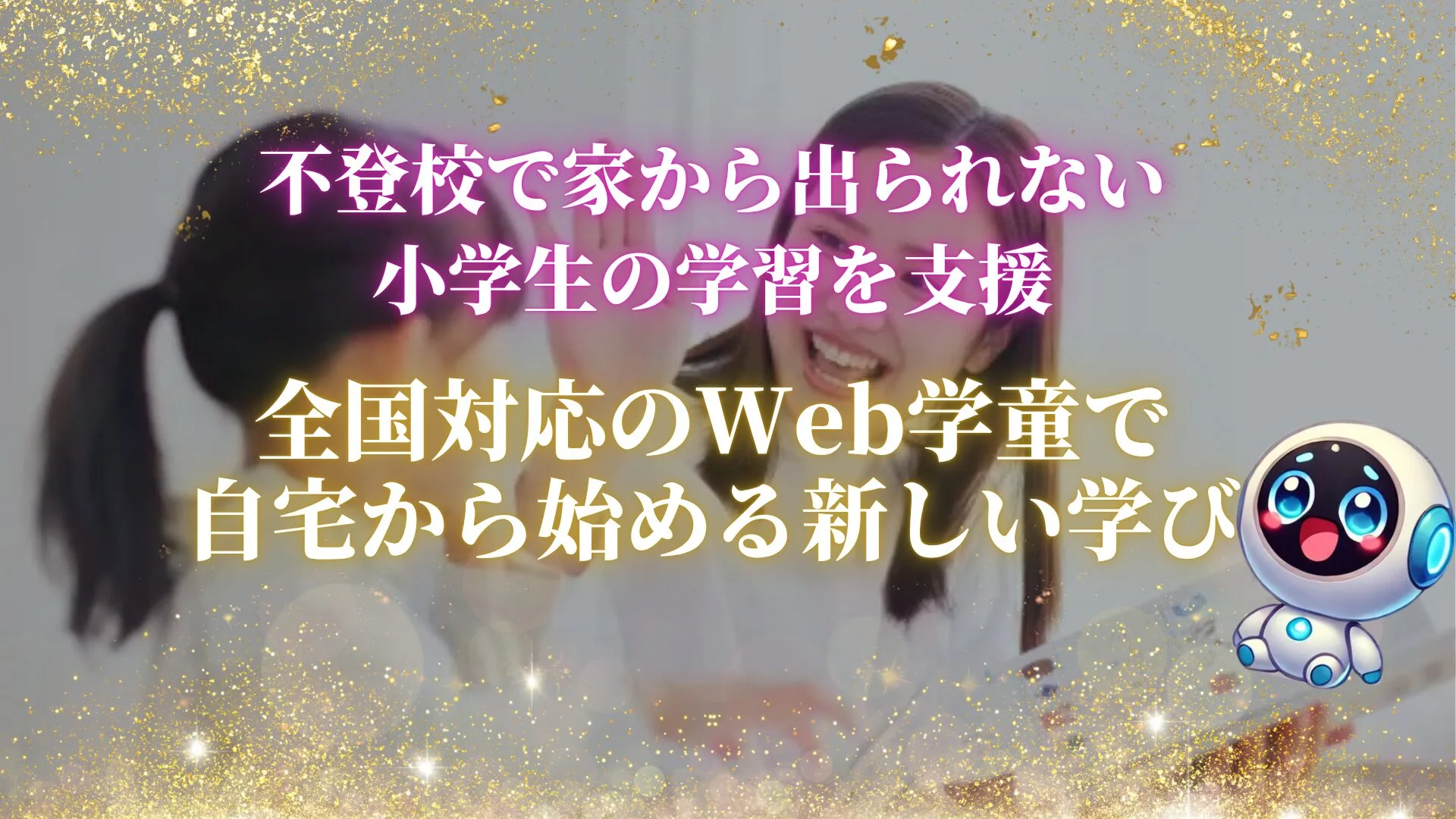不登校で家から出られない小学生の学習課題と親の悩み
お子さんが学校に行けなくなってから、どのくらいの時間が経ちましたか。「今日も学校に行けなかった」という現実に直面するたび、親として何ができるのか、どうすればいいのか、答えの見えない不安に押しつぶされそうになることもあるでしょう。
不登校は決して珍しいことではありません。文部科学省の調査によると、小学生の不登校児童数は年々増加傾向にあり、2022年度には約10万人を超えています。(引用元:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00005.htm)
北海道から沖縄まで、全国どこの地域でも同じような悩みを抱えている家庭があります。大切なのは、お子さんも親御さんも、決して一人ではないということです。
学習の遅れへの不安と焦り
「みんなが学校で勉強している間、うちの子は何も学んでいない」そんな焦りを感じていませんか。実際、東京都内のある保護者の方からは「毎日学校からプリントが届くけれど、子どもは見向きもしない。このままでは、どんどん遅れていく一方です」という声が寄せられています。
学習の遅れは、単に知識の問題だけではありません。「できない」という経験が積み重なることで、子どもの自己肯定感はさらに下がり、学習への意欲そのものを失ってしまう可能性があります。特に小学生の時期は、基礎学力を身につける大切な時期。算数の九九や漢字の読み書きなど、この時期に身につけるべき基礎が抜け落ちると、その後の学習にも大きな影響を与えてしまいます。
しかし、焦りは禁物です。無理に勉強させようとすると、かえって子どもの心を閉ざしてしまうことも。大切なのは、子どものペースを尊重しながら、少しずつでも学習の機会を作っていくことです。
子どもの将来への心配
「このまま不登校が続いたら、この子の将来はどうなるんだろう」多くの保護者の方が抱える、最も大きな不安かもしれません。中学受験を考えている家庭では、その計画を見直さざるを得なくなることも。名古屋市のある保護者は「周りの子は塾に通い始めているのに、うちの子は家から一歩も出られない。この差は、きっと取り返しがつかないんじゃないか」と涙ながらに語っていました。
確かに、不登校の期間が長引けば長引くほど、学習面での遅れは大きくなります。しかし、人生は学校だけで決まるものではありません。今は辛い時期かもしれませんが、適切なサポートがあれば、子どもたちは必ず自分のペースで成長していきます。実際、不登校を経験した後、自分に合った学習方法を見つけて、大きく成長した子どもたちもたくさんいます。
大切なのは、「今」できることから始めること。将来への不安に押しつぶされるのではなく、今日一日、子どもが少しでも前に進めるような環境を整えることが、結果として明るい未来につながっていくのです。
親だけでサポートすることの限界
「私が教えればいい」そう思って、家庭学習を始めた親御さんも多いでしょう。しかし、実際にやってみると、想像以上に難しいことに気づきます。大阪府のあるお母さんは「最初は張り切って教材を買い揃えたんです。でも、子どもは私の言うことを聞かないし、つい感情的になってしまって。結局、親子関係まで悪くなってしまいました」と振り返ります。
親が教師役を担うことの難しさは、単に教え方の問題だけではありません。日常生活の中で、親は「叱る」「褒める」「世話をする」など、様々な役割を担っています。そこに「教える」という役割が加わると、子どもは混乱してしまうことがあります。また、親自身も仕事や家事に追われる中で、毎日決まった時間に学習指導をすることは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。
さらに、不登校の子どもたちは、学習以前に心のケアが必要な場合が多くあります。専門的な知識や経験がない中で、適切なサポートをすることは容易ではありません。「もっと早く、プロの力を借りればよかった」という声は、実は多くの保護者から聞かれる言葉なのです。
自宅でできる学習支援の選択肢

不登校で家から出られないお子さんのために、自宅でできる学習支援にはどのような選択肢があるのでしょうか。「うちの子に合う方法はあるのかな」と悩んでいる保護者の方も多いはずです。ここでは、代表的な3つの方法について、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
福岡県のある保護者の方は「色々な方法を試してみたけれど、なかなか続かなくて。でも、諦めずに探し続けたら、うちの子に合う方法が見つかりました」と話しています。大切なのは、お子さんの性格や状況に合わせて、最適な方法を選ぶこと。一つの方法がうまくいかなくても、それは失敗ではなく、お子さんに合う方法を見つけるための大切なステップなのです。
家庭教師のメリット・デメリット
家庭教師は、不登校の子どもたちにとって身近な学習支援の一つです。最大のメリットは、マンツーマンで丁寧に教えてもらえること。子どものペースに合わせて、分からないところは何度でも説明してもらえます。「先生が家に来てくれるから、外出の準備をする必要もないし、子どもも安心して勉強できています」という声も聞かれます。
しかし、デメリットも存在します。まず、料金が高額になりがちなこと。週2回、1回2時間の指導を受けると、月額4〜8万円程度かかることも珍しくありません。また、相性の良い先生を見つけるのが難しいという課題もあります。
北海道のある家庭では「3人目の先生でようやく子どもが心を開いてくれました。それまでは、先生が来る日は子どもが部屋から出てこなくて」という経験談も。
さらに、家庭教師は基本的に学習指導が中心となるため、不登校の根本的な問題へのアプローチは限定的になりがちです。心のケアや生活リズムの改善など、総合的なサポートを求める場合は、他の選択肢も検討する必要があるでしょう。
通信教育・タブレット学習の特徴
タブレット学習や通信教育は、自分のペースで学習を進められる点が大きな魅力です。最近では、AIを活用した個別最適化学習も増えており、子どもの理解度に応じて問題の難易度が自動調整される教材もあります。「ゲーム感覚で勉強できるから、うちの子も楽しんでやっています」という声も。月額料金も3,000円〜1万円程度と、家庭教師に比べて手頃な価格設定となっています。
ただし、自己管理能力が求められるという難しさがあります。東京都内の小学4年生の保護者は「最初の1週間は張り切ってやっていたけど、だんだんタブレットを開かなくなって。結局、親が声をかけないと勉強しません」と悩みを打ち明けています。また、分からないところがあってもすぐに質問できない、モチベーションの維持が難しいといった課題も。
不登校の子どもたちの場合、学習への意欲自体が低下していることも多く、自主的に教材に取り組むことが難しいケースが少なくありません。保護者のサポートが不可欠となりますが、それが親子関係の負担になってしまうこともあるのです。
オンライン学習支援「Web学童」とは
Web学童は、これまでの習い事サービスとは全く異なる新しいタイプのオンライン学習支援サービスです。従来の学習支援とは異なり、「学童」という名前が示すように、単なる学びの場ではなく、子どもたちの「居場所」となることを目指しています。
このサービスの最大の特徴は、学習支援と心のケアを両立させている点です。専門の研修を受けたスタッフが、オンラインを通じて子どもたち一人ひとりに寄り添います。「今日はどんな気分?」から始まり、その日の子どもの状態に合わせて、学習内容や進め方を柔軟に調整。名古屋市の小学3年生の保護者からは「うちの子、画面越しでも先生とお話しするのを楽しみにしているんです。勉強だけじゃなくて、好きなゲームの話とかもしてくれるみたいで」という声が届いています。
また、保護者へのサポートも充実しており、定期的な面談や日々の相談にも対応。大阪府のお母さんは「子どもの様子を共有してくれるだけでなく、私の不安にも寄り添ってくれる。一人で抱え込まなくていいんだって、心が軽くなりました」と話しています。料金も月額9,000円台からと、家庭教師よりも手頃で、全国どこからでも利用できる点も大きな魅力となっています。
Web学童が不登校の子どもに選ばれる5つの理由

なぜ、多くの不登校の家庭がWeb学童を選んでいるのでしょうか。それは、このサービスが不登校の子どもたちと保護者の「本当に必要としているもの」に寄り添っているからです。ここでは、実際に利用している家庭の声を交えながら、Web学童が選ばれる5つの理由を詳しくご紹介します。
「最初は半信半疑でした」という福岡県の小学5年生のお母さんも、実際に利用を始めると、その良さを実感されています。
1. 自宅から一歩も出ずに始められる安心感
不登校の子どもたちにとって、家の外に出ることは想像以上に高いハードルです。「玄関まで行っただけで動悸がする」「外の音が怖い」そんな子どもたちも少なくありません。Web学童なら、安心できる自宅の環境のまま、新しい学びの世界に一歩を踏み出すことができます。
北海道札幌市の小学2年生の例では、最初はパジャマのままで画面の前に座ることから始めました。「着替えなくていいよ、そのままで大丈夫」というスタッフの言葉に、子どもも保護者も驚いたそうです。しかし、これこそがWeb学童の考え方。まずは、子どもが「できる」と感じられる小さな一歩から始めることが大切なのです。
時間が経つにつれて、その子は自然と身だしなみを整えるようになり、今では毎朝決まった時間に自分から準備をするように。「家から出なくていいという安心感があるからこそ、子どもは前に進めたんだと思います」とお母さんは話しています。物理的な移動のストレスがないことで、子どもたちは学習そのものに集中できるようになるのです。
2. 専門スタッフによる個別対応
Web学童のスタッフは、単に勉強を教えるだけの存在ではありません。不登校支援の専門研修を受け、子どもの心理や発達について深い理解を持つプロフェッショナルも在籍しています。一人ひとりの子どもの特性や状況を丁寧に把握し、その子に最適な関わり方を模索します。
「うちの子は集中力が続かなくて、5分で飽きてしまうんです」という相談に対して、スタッフは60分の学習時間を15分×4回に分割。間に子どもの好きな話題を挟みながら、無理なく学習を進める工夫をしました。東京都のある保護者は「こんな柔軟な対応、学校では絶対にしてもらえない。うちの子のペースを本当に大切にしてくれているんだなって感じます」と感謝の言葉を述べています。
また、スタッフは必要に応じて臨床心理士などの専門家とも連携を取りながら、より良いサポートを提供しています。この専門性の高さが、多くの家庭から信頼される理由の一つとなっています。
3. 学習だけでなく心のケアも重視
不登校の背景には、学習の遅れだけでなく、様々な心の問題が隠れていることがあります。友達関係の悩み、家族との関係、自己肯定感の低下など、子どもたちは多くの重荷を背負っています。Web学童では、これらの心の問題にも丁寧に向き合います。
名古屋市の小学4年生の事例では、最初の1ヶ月は勉強の話は一切せず、好きなアニメやゲームの話ばかりしていました。保護者は「本当にこれでいいの?」と不安に思ったそうですが、スタッフは「まずは信頼関係を築くことが大切です」と説明。実際、2ヶ月目から子どもは自分から「算数やってみようかな」と言い出したのです。
「認められている」「受け入れられている」という感覚は、子どもたちの心を癒し、前に進む力を与えます。大阪府のお父さんは「勉強ができるようになったことも嬉しいけど、何より子どもの表情が明るくなったことが一番嬉しい」と話しています。学習支援を通じて、子どもたちの心も育んでいく。それがWeb学童の大切な役割なのです。
4. 子どものペースに合わせた柔軟なプログラム
「今日は調子が悪いから休みたい」「この教科は苦手だから違うことをしたい」Web学童では、こうした子どもの声を大切にします。画一的なカリキュラムではなく、その日その時の子どもの状態に合わせて、学習内容や方法を柔軟に調整していきます。
ある日は30分みっちり算数に取り組み、別の日は10分だけ漢字練習をして、残りの時間は工作や読み聞かせ。福岡県の小学1年生の保護者は「学校だったら『みんなと同じように』って言われるけど、Web学童は本当にうちの子のペースを尊重してくれる。だから、子どもも安心して参加できるんです」と話します。
また、学習の進度も子どもに合わせて調整。学年を超えて基礎から学び直すことも、逆に得意な分野は先に進むことも可能です。このような柔軟性があるからこそ、子どもたちは「できない」というプレッシャーから解放され、「できるかも」という希望を持てるようになるのです。
5. 全国どこからでも利用可能
「うちの地域には、不登校支援の施設がない」地方に住む家庭からよく聞かれる悩みです。確かに、都市部に比べて地方では支援の選択肢が限られることが多いのが現実。しかし、Web学童なら、インターネット環境さえあれば、北海道の山間部でも、沖縄の離島でも、全国どこからでも質の高い支援を受けることができます。
実際に、鹿児島県の離島に住む小学3年生も利用しています。「島には塾もないし、家庭教師も呼べない。でも、Web学童なら東京の先生と毎日お話しできる。地理的な制約を感じさせないのが本当にありがたい」とお母さんは話します。
また、転勤族の家庭にとっても大きなメリットが。「引っ越しのたびに新しい支援先を探すのは大変だったけど、Web学童なら引っ越してもそのまま続けられる。子どもにとっても、慣れ親しんだ先生と継続的に関われることが心の支えになっています」という声も。場所に縛られない支援だからこそ、子どもたちに安定した学びの環境を提供できるのです。
Web学童と家庭教師・他サービスとの違い
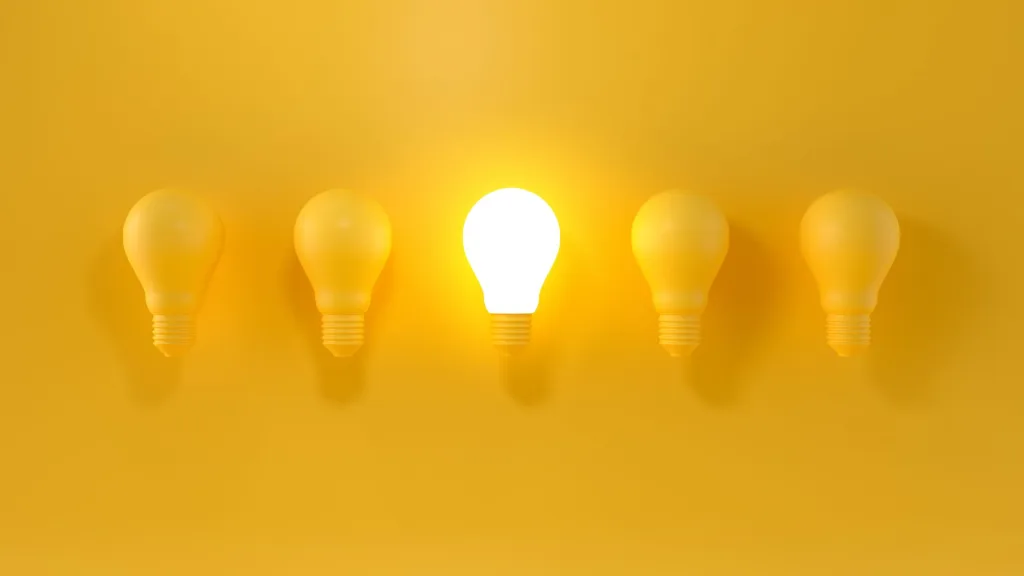
「Web学童って、結局は家庭教師やタブレット学習と何が違うの?」そんな疑問を持つ方も多いでしょう。確かに、どれも自宅で学習できるという点では同じように見えるかもしれません。しかし、実際のサービス内容や子どもへのアプローチ方法には大きな違いがあります。ここでは、それぞれの特徴を比較しながら、Web学童ならではの強みを詳しく見ていきましょう。
東京都のあるお母さんは「最初は家庭教師を検討していたけど、Web学童の説明を聞いて、こっちの方がうちの子に合っていると思いました」と話します。大切なのは、お子さんの状況や性格、ご家庭の事情に合わせて、最適なサービスを選ぶこと。それぞれの違いを理解することで、より良い選択ができるはずです。
料金体系の比較
まず気になるのが料金面での違いです。家庭教師の場合、週2回・各2時間の指導で月額4〜8万円程度が相場。プロ家庭教師や医学部生など、講師のレベルによってはさらに高額になることも。また、交通費や教材費が別途かかる場合もあり、トータルコストは意外と高くなりがちです。
一方、タブレット学習や通信教育は月額3,000円〜1万円程度と手頃ですが、質問対応や個別指導は基本的に含まれていません。オプションで個別指導を追加すると、結局2〜3万円かかることも。「安いと思って始めたけど、結局サポートが必要で追加料金がかさんでしまった」という声も聞かれます。
Web学童の料金は月額9,000円から。一見すると「タブレット学習より高い」と感じるかもしれませんが、これには専門スタッフによる個別対応、心のケア、保護者サポートなど、総合的な支援が含まれています。
名古屋市の保護者は「家庭教師の半額以下で、もっと手厚いサポートが受けられる。コストパフォーマンスは断然Web学童の方が良い」と評価しています。利用回数や時間も柔軟に調整でき、必要に応じてプランを変更できる点も、家計に優しいポイントです。
サポート内容の違い
サービスごとのサポート内容の違いは、料金以上に重要なポイントかもしれません。家庭教師は基本的に「教科指導」に特化しており、決められた時間内で効率的に勉強を教えることが主な役割です。不登校の背景にある心理的な問題や、生活リズムの改善などは専門外となることが多いでしょう。
タブレット学習では、AIによる学習進度の管理や、動画解説などの機能は充実していますが、人によるサポートは限定的。「分からないところを質問したくても、返事が来るまで時間がかかる」「機械的な対応で、子どもの気持ちに寄り添ってもらえない」といった不満も。
これに対してWeb学童は、学習支援はもちろん、生活リズムの確立、心のケア、ソーシャルスキルの向上など、不登校の子どもに必要な支援を包括的に提供します。大阪府の小学5年生の保護者は「勉強だけじゃなくて、趣味の話から、友達との関わり方まで、本当に幅広くサポートしてくれる。まるで、もう一つの学校があるみたい」と話しています。また、保護者向けの定期面談や、緊急時の相談対応など、家族全体を支える体制が整っている点も大きな特徴です。
子どもへの接し方の特徴
最も大きな違いは、子どもへの接し方にあるかもしれません。家庭教師の場合、限られた時間で成果を出すことが求められるため、どうしても「教える」ことが中心になりがちです。「宿題やってきた?」「ここ、前回も間違えたよね」といった指導的な関わりが多くなることも。
タブレット学習では、そもそも人との関わりがほとんどありません。「間違えてもアニメーションが励ましてくれるけど、やっぱり人じゃないから…」という子どもの声も。特に不登校の子どもたちにとって、人との温かい関わりは学習意欲を支える大切な要素です。
Web学童のスタッフは、まず子どもとの信頼関係を築くことを最優先に考えます。「今日は何して遊んだ?」「好きなYouTuberの新しい動画見た?」など、子どもの興味関心から会話を始め、自然な流れで学習につなげていきます。福岡県の小学2年生は「先生は友達みたい。勉強してるって感じがしない」と話しています。この「教える人」ではなく「一緒に学ぶ人」という立ち位置が、子どもたちの心を開き、主体的な学びを引き出すのです。
Web学童の具体的な支援内容

「実際のところ、Web学童ではどんなことをするの?」利用を検討している保護者の方が最も知りたいことの一つでしょう。ここでは、Web学童の具体的な学習支援の方法、そして保護者へのサポート体制まで、詳しくご紹介します。
学習支援の進め方
Web学童の学習支援は、「教える」よりも「体験・経験」を重視しています。
例えば、算数が苦手な子には、いきなり問題集を解かせるのではなく、「お買い物ゲーム」から始めます。「100円のお菓子を3個買ったらいくら?」という具体的な場面から、掛け算の概念を理解していきます。名古屋市の小学4年生の保護者は「学校では『九九を覚えなさい』の一点張りだったけど、Web学童では『なぜ掛け算が必要なのか』から教えてくれた。理解が深まったようで、自分から九九の練習をするようになりました」と喜んでいます。
また、つまずきポイントの発見と対処も丁寧に行います。「分数が分からない」という子どもに対して、実はその前段階の「割り算の概念」が曖昧だったことを発見。そこから学び直すことで、分数もスムーズに理解できるようになりました。このような「学び直し」は、学年や進度にとらわれずに行えるのが、Web学童の強みです。
さらに、学習の記録は全てデジタルで管理され、子どもの成長が可視化されます。「先月は漢字を10個しか書けなかったけど、今月は30個も書けるようになったね!」という具体的なフィードバックが、子どもたちの自信につながります。大阪府の小学2年生は「自分の『できたノート』を見るのが楽しみ」と話しており、学習へのモチベーション維持にも効果的です。
保護者へのフォロー体制
不登校の子どもを支えるためには、保護者のサポートも欠かせません。Web学童では、子どもの支援と同じくらい、保護者へのフォローを重視しています。「親の不安が子どもに伝わってしまう」そんな悪循環を断ち切るためにも、保護者の心のケアは重要なのです。
まず、週1回の定期報告では、子どもの様子や学習の進捗を詳しく共有。「今週は算数の掛け算に挑戦しました。最初は嫌がっていましたが、ゲーム形式にしたら楽しそうに取り組んでいました」といった具体的なエピソードと共に、次週の目標も相談しながら決めていきます。福岡県のお母さんは「学校の先生よりも、うちの子のことをよく見てくれている。毎週の報告が楽しみです」と話しています。
また、月1回の保護者面談では、じっくりと時間をかけて相談に乗ります。「最近、子どもにどう接していいか分からなくて」「このままで本当に大丈夫なのか不安で」そんな率直な気持ちを受け止め、一緒に解決策を考えます。専門的な知識を持つスタッフだからこそできる、的確なアドバイスが保護者の支えとなっています。
さらに、緊急時の相談体制も整っています。「子どもが急に泣き出して止まらない」「学校から進路の話をされて混乱している」そんな時は、LINEやメールですぐに相談可能。東京都の保護者は「夜中に子どもがパニックになった時、すぐに相談できて本当に助かりました。一人じゃないって思えることが、何より心強い」と振り返ります。
利用開始までの流れと料金プラン

「興味はあるけど、どうやって始めればいいの?」「料金はどのくらいかかるの?」ここでは、Web学童の利用を検討している方のために、具体的な申し込み方法から料金プラン、必要な準備まで、分かりやすくご説明します。
多くの保護者が最初に感じるのは「うちの子に合うかどうか」という不安です。北海道のお父さんも「オンラインで本当に大丈夫なのか、正直半信半疑でした」と話していました。そんな不安を解消するために、Web学童では充実した体験プログラムを用意しています。まずは気軽に試してみることから始めてみませんか。
無料相談・体験の申し込み方法
Web学童では、いきなり本申し込みをする必要はありません。まずは無料相談から始めることができます。申し込みは公式LINEから1タップで予約をするだけ。24時間以内に専門スタッフから連絡が来ます。
初回の相談は、保護者の方だけでもOK。「子どもはまだ他人と話すのが難しくて」という場合でも安心です。約30分の相談では、お子さんの現在の状況、これまでの経緯、ご家庭の希望などをじっくりお聞きします。名古屋市のお母さんは「こんなに丁寧に話を聞いてもらえたのは初めて。それだけで、心が軽くなりました」と話しています。
その後、無料体験の日時を決めていきます。体験は1時間の講義を2回。実際のプログラムを体験しながら、お子さんとサービスの相性を確認できます。「最初は5分しか画面の前にいられなかったけど、3日目には30分も参加できた」そんな小さな成長も一緒に喜びます。
もちろん、体験後に「やっぱり合わない」と感じたら、無理に継続する必要はありません。大阪府の保護者は「断るのが申し訳ないと思っていたけど、『お子さんに合う方法を一緒に考えましょう』と言ってもらえて、プレッシャーを感じませんでした」と安心感を語っています。
料金プランの詳細
Web学童の料金プランは、一般的に年間プランもしくは月額プランに応じて設定されています。
年間プラン
・月額:9,000〜円(税別)
・月間指導時間:約10時間
・利用時間:24時間
※注意事項:途中解約不可
月額プラン
・月額:23,000円(税別)
・頻度:週2回
・利用時間:24時間
これらの基本料金には、学習指導、グループ活動、保護者面談などが含まれております。追加料金が発生する場合は、特別イベントや個別教材などに限定されることが多いです。割引制度として、兄弟割引、紹介割引などを設けております。
必要な環境・準備するもの
Web学童を始めるために必要なものは、意外とシンプルです。まず必須なのは、インターネットに接続できるパソコンかタブレット。スマートフォンでも可能ですが、画面が小さいため、学習には向きません。「うちにはパソコンがなくて」という方も、最近は2〜3万円程度で十分な性能のタブレットが購入できます。
インターネット環境は、一般的な光回線やWi-Fiがあれば十分。「うちのネット、遅いんだけど」という心配も、実際にはそれほど高速な回線は必要ありません。ビデオ通話ができる程度の速度があれば問題なく利用できます。
カメラとマイクは、最近のパソコンやタブレットには標準装備されていることがほとんど。別途購入する必要はありません。ただし、「音が聞き取りにくい」という場合は、1,000円程度のヘッドセットがあると便利です。名古屋市の保護者は「100均のイヤホンマイクでも十分でした」と話しています。
学習に使う教材は、基本的にWeb学童側で用意。必要に応じてプリントアウトする程度で、高額な教材を購入する必要はありません。ノートと筆記用具があれば、すぐに始められます。大阪府のお母さんは「こんなに準備が簡単だとは思わなかった。もっと早く始めればよかった」と振り返ります。
よくある質問

Web学童の利用を検討する際、多くの保護者から寄せられる質問があります。ここでは、特に多い2つの質問について、実際の事例を交えながら詳しくお答えします。同じような不安を抱えている方も多いはず。一つひとつ、丁寧に解消していきましょう。
「聞きたいことはたくさんあるけど、こんなこと聞いていいのかな」そんな遠慮は不要です。どんな小さな疑問でも、Web学童のスタッフは真摯に対応します。東京都のお父さんは「些細なことまで丁寧に答えてもらえて、安心して利用を決められました」と話しています。
子どもが画面の前に座れるか心配です
「うちの子、人と話すのが苦手で、画面の前に座ることすらできないかも」これは、最も多く寄せられる心配の一つです。実際、不登校の子どもたちの中には、対人関係に強い不安を感じている子も少なくありません。でも、ご安心ください。Web学童では、そんな子どもたちのペースに合わせた段階的なアプローチを行っています。
北海道の小学3年生のBさんの例をご紹介しましょう。最初の1週間は、カメラをオフにして音声だけの参加。それも最初は5分が限界でした。スタッフは焦ることなく、「今日は5分も頑張れたね!明日は6分挑戦してみる?」と優しく声をかけます。2週間後には音声で15分会話ができるように。1ヶ月後には、ついにカメラをオンにして顔を見せてくれました。
「段階を踏むことの大切さを実感しました」とBさんのお母さん。「最初から『カメラをつけなさい』と言っていたら、きっと逃げ出していたと思います」。現在のBさんは、毎日1時間以上Web学童に参加し、スタッフとの会話を楽しみにしているそうです。
また、最初は保護者が隣に座っていてもOK。福岡県の小学1年生は、3ヶ月間お母さんと一緒に参加していました。「徐々に私の存在を忘れて、先生との会話に夢中になっていく姿を見て、成長を感じました」とお母さんは振り返ります。子どもが安心できる環境から始めて、少しずつ自立を促していく。それがWeb学童のアプローチです。
最後に
不登校で家から出られないお子さんを持つ保護者の皆さん、今日も本当にお疲れ様です。この記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございました。きっと、お子さんのために「何かできることはないか」と真剣に考えていらっしゃることでしょう。
Web学童は、そんな皆さんの思いに寄り添い、お子さんが自分らしく成長できる場所を提供したいと考えています。完璧を求める必要はありません。今、できることから、一歩ずつ始めてみませんか。
まずは無料相談から。あなたとお子さんの「今」を、ぜひお聞かせください。専門スタッフが、丁寧にお話を伺い、最適なサポート方法を一緒に考えます。LINEでの相談も受け付けているので、電話が苦手な方も安心です。
詳しい資料をご希望の方は、公式サイトから資料請求も可能です。より詳しいプログラム内容や、実際の利用者の声などをまとめた資料を、無料でお送りしています。
お子さんの笑顔を取り戻すために、私たちにお手伝いさせてください。Web学童で、新しい一歩を踏み出してみませんか。