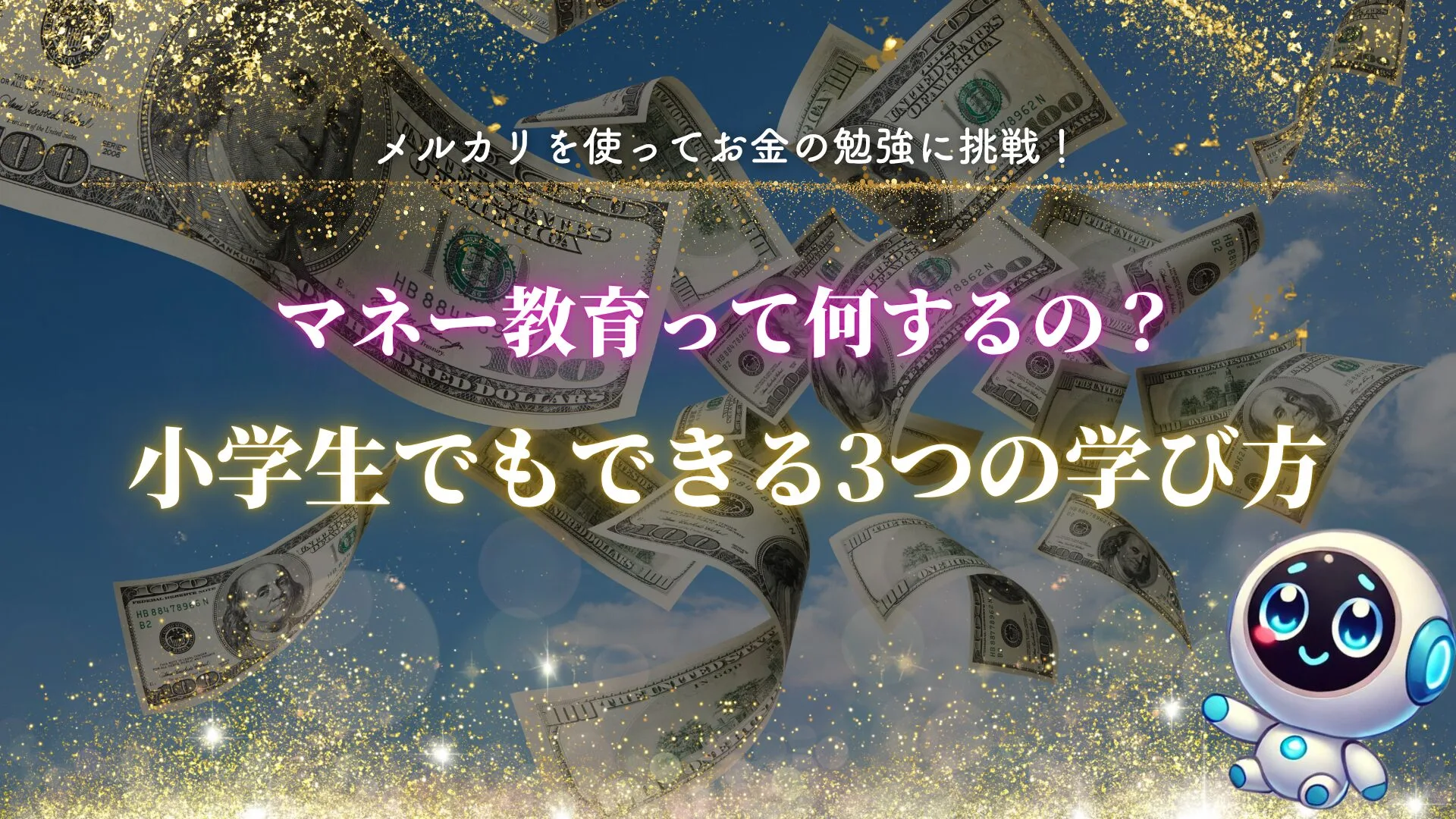「将来、お金で苦労させたくない」親なら誰もが願うこと。でも…

「ママ、これ買って!」スーパーのお菓子売り場で、子どもが無邪気にカゴに入れてくるキャラクターもののお菓子。お年玉をもらっても、計画を立てるわけでもなく、あっという間に欲しかったゲームソフトに消えていく…。
お子様のそんな姿を見て、「この子は、お金の大切さがわかっているのだろうか」「将来、ちゃんとお金の管理ができる大人になれるのだろうか」と、ふと不安がよぎることはありませんか?
「将来、お金で苦労だけはさせたくない」。これは、子を持つ親なら誰もが抱く、切実な願いです。そのために、小さいうちから正しい金銭感覚を身につけさせたい、と考えるのは当然のことでしょう。
しかし、その一方で、「いざ、お金の話をしようと思っても、何からどう教えればいいのかわからない…」「そもそも、自分自身が学校できちんとお金のことを習った経験がないのに、子どもに正しく教えられる自信がない…」。そんな風に、戸惑いや難しさを感じている方も多いのではないでしょうか。
「おこづかい制を始めたものの、ルールが曖昧ですぐに崩壊してしまった」「キャッシュレス決済ばかりで、子どもがお金を使っている感覚を持っているのか不安です」。その悩み、そして自信のなさ、決してあなただけではありません。全国の保護者様が、手探り状態で家庭でのマネー教育に向き合っているのです。
なぜ今、小学生からマネー教育が必要なのか?

「子どものうちは、お金の心配なんてさせずに、のびのびと育ってほしい」。そう考えるお気持ちも、とてもよくわかります。しかし、残念ながら、私たち親世代が子どもだった頃とは、お金を取り巻く環境が大きく変わってしまいました。今、小学生のうちからマネー教育を始めることには、差し迫った重要性があるのです。
第一に、キャッシュレス化の急速な進展です。スマホ決済や交通系ICカードが当たり前になり、子どもたちがお金の「形」を見ることなく、高額な買い物ができるようになりました。お札や硬貨をやり取りする「痛み」を感じにくいため、お金を使っているという感覚が希薄になりがちです。だからこそ、見えないお金をきちんと管理し、価値を理解する訓練が、より一層必要になっています。
第二に、社会全体の金融リテラシー向上への動きです。2022年度から施行された文部科学省の高等学校学習指導要領により、高校の家庭科で「資産形成」の視点を含んだ金融教育が必修化されました。(出典:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51840730W9A101C1000000/)これは、国が「自分のお金は自分で守り、育てる時代だ」という明確なメッセージを発していることに他なりません。高校生になって突然、投資やライフプランニングの話をされても、土台となる金銭感覚が養われていなければ、子どもたちは戸惑うばかりでしょう。小学生のうちから、その素地を育んでおくことが、将来の学びをスムーズにする鍵となります。
そして最後に、マネー教育は単なる「お金の知識」を教えるものではなく、変化の激しい社会を「生き抜く力」そのものを育むからです。限られたおこづかいでやりくりする計画性、目標のために我慢する自制心、お手伝いを通じて得る労働への対価の感覚。これらはすべて、社会に出てから必ず必要になる大切なスキルです。お金について学ぶことは、人生を豊かに生きるための知恵を学ぶことなのです。
家庭でできる!小学生のマネー教育3つのステップ

「マネー教育の重要性はわかったけれど、じゃあ具体的に家庭で何をすればいいの?」。ここからは、今日からでも始められる、小学生向けのマネー教育を具体的な3つのステップに分けてご紹介します。難しく考える必要はありません。お子様の成長に合わせて、ゲーム感覚で楽しく取り入れてみてください。
ステップ①《使う力》:「おこづかい」と「買い物」で学ぶ
お金の教育の第一歩は、「使う力」を養うことです。その最高の教材が「おこづかい」です。
まず、おこづかいのルールを決めましょう。毎月決まった額を渡す「定額制」は、予算管理能力が身につきやすいメリットがあります。
一方、お手伝いの内容に応じて金額が変わる「報酬制」は、労働の対価を学ぶのに適しています。ご家庭の方針に合わせて選び、一度決めたルールは守ることが大切です。
次に、おこづかい帳をつけさせましょう。最初は簡単なもので構いません。「いつ、何に、いくら使ったか」を記録するだけで、自分のお金の流れが可視化され、「無駄遣いだったかも」と自分で気づけるようになります。
そして、一緒に買い物に行くことも重要です。「お菓子は100円までね」と予算を決め、その中で子ども自身に「欲しいもの」を選ばせるのです。値段を見比べること、予算内でやりくりすること、そして「本当に必要なもの」と「ただ欲しいだけのもの」の違いを考える、最高のトレーニングになります。
ステップ②《稼ぐ力》:「お手伝い」や「フリマ体験」で学ぶ
お金は、ただ待っていればもらえるものではなく、労働や価値を提供した対価として得られるものだ、という感覚を養うのがこのステップです。
家庭内でのお手伝いに、報酬を設定してみましょう。「お風呂掃除50円」「新聞を取ってくる10円」など、家族の役割として当然のものは無償とし、それ以上の特別な労働に対して報酬を支払うのがポイントです。
もう少し大きくなったら、「フリマアプリでお金の勉強」も効果的です。使わなくなったおもちゃや読まなくなった本などを、親子で一緒に出品してみるのです。商品の写真を撮り、説明文を考え、値段を設定し、売れたら梱包して発送する。この一連のプロセスは、まさにビジネスの縮図です。「どうすれば魅力的に見えるか」「いくらなら買ってもらえるか」を考える経験は、お金を「稼ぐ」ことの大変さと面白さを同時に教えてくれます。
ただし、フリマアプリは規約で未成年者の利用が禁止されている場合が多く、金銭トラブルや個人情報漏洩のリスクも伴います。必ず保護者のアカウントを使い、規約を遵守した上で、すべてのやり取りを監督することが絶対条件です。
ステップ③《増やす・守る力》:「銀行」と「投資のキホン」で学ぶ
お金は、ただ貯めるだけでなく、「増やす」ことや「守る」こともできる、という視点を教えるのが最終ステップです。
まずはお子様専用の銀行口座を作り、お年玉などを一緒に預けに行ってみましょう。「銀行に預けておくと、少しだけ『利子』というおまけがもらえるんだよ」と、金利の概念を優しく教えてあげます。
そして、「投資のキホン」に触れさせてあげるのも良いでしょう。例えば、1株から購入できるサービスを利用して親子で応援したい企業の株主になる方法もあります。株価の変動は経済を学ぶ良い機会ですが、**元本割れのリスクがあることも必ず伝えましょう。あるいは、実際に投資はせず、親子で特定の企業の株価の動きをニュースと合わせて追いかけるだけでも、立派な経済学習になります。
>>Web学童で実際に使用しているマネー教育資料のダウンロードはこちら
家庭教育の”落とし穴”。親が教えるからこそ難しいこと

ここまで、ご家庭で実践できるマネー教育の方法をご紹介してきました。おこづかいのルールを決め、一緒にお金の流れを管理し、労働の対価を教える。これらの取り組みは、間違いなくお子様の金融リテラシーの土台を築く上で非常に重要です。
しかし、その一方で、家庭でのマネー教育には、親が教えるからこその”落とし穴”が存在することも事実です。もし、あなたが「うちのマネー教育、なんだかうまくいかないな…」と感じているとしたら、それはあなたの教え方が悪いのではなく、家庭教育が持つ構造的な難しさに直面しているのかもしれません。
例えば、お子様のおこづかいの使い道に、つい口を出してしまい「そんな無駄なもの買って!」と感情的に叱ってしまった経験はありませんか。子どもの自主性を育てたいのに、矛盾した行動をとってしまうのは、親心ゆえの難しさです。
また、親が教える知識は、どうしても断片的になりがちです。「おこづかい」や「貯金」の話はできても、それが社会の経済活動や、将来の資産形成とどう繋がっているのか、体系的に教えるのは非常に困難です。さらに言えば、私たち親自身が持つ「お金は汗水流して稼ぐもの」「投資は怖いもの」といった価値観(マネースクリプト)を、無意識のうちに子どもに押し付けてしまう危険性もあります。
良かれと思ってやっている家庭でのマネー教育が、かえってお金に対するネガティブなイメージを植え付けてしまったり、親子の関係をギクシャクさせてしまったりするのは、とても悲しいことです。だからこそ、家庭での実践をベースにしつつ、客観的で体系的な知識を与えてくれる「第三者の力」を上手に借りることが、これからのマネー教育を成功させる鍵となるのです。
これからの正解は「Web学童」で学ぶ、実践型マネー教育

家庭でのマネー教育が持つ難しさ。それを解決し、お子様が本当に「生きる力」としてのお金の知識を身につけるための新しい選択肢。それが、私たちの「Web学童」が提供する、実践型のマネー教育プログラムです。
「Web学童」のマネー教育は、単に「お金とは何か」を座学で教えるものではありません。子どもたちが主役となり、仲間と協力しながら、まるで社会の縮図のようなリアルな経済活動を「体験」することに重きを置いています。知識のインプットだけでなく、実際に頭と体を動かして汗をかくことで、お金の本質を肌感覚で学んでいく。これこそが、これからの時代に求められるマネー教育の有力な選択肢の一つだと、私たちは考えています。
フリマアプリで実際に「稼ぐ」体験をする
Web学童では、「経験」をとても重視しています。そのなかでも、フリマサイトを活用して実際にお金を稼ぐ経験をすることがとても人気です。
この体験を通じて、子どもたちは多くのことを学びます。どうすれば商品が売れるのかを考える「マーケティング思考」。限られた予算の中で材料を仕入れる「コスト意識」。商品を売りやすく魅せるための「コピー能力」。たとえ売れなかった失敗も成功も、すべてが子どもたちの血肉となり、お金を「稼ぐ」ことの難しさと面白さを教えてくれます。
プロ(FP)や仲間との対話で「お金の哲学」を育む
「Web学童」では、ファイナンシャル・プランナー(FP)などの専門家を招き、「お金とはなにか?」「銀行ってどういう仕組みなの?」といった、子どもたちの素朴な疑問に答える時間も設けています。客観的で正しい知識を、プロから直接学ぶことができる貴重な機会です。
しかし、それ以上に私たちが大切にしているのは、子どもたち同士の「対話」です。例えば、「もし100万円あったら、何に使う?」というテーマで、グループディスカッションを行います。東京の子は「投資する」、大阪の子は「みんなが楽しめるイベントを開く」、福岡の子は「困っている人に寄付する」など、様々な意見が飛び交います。お金に「絶対の正解」はありません。多様な価値観に触れることで、子どもたちは「自分にとって、お金とは何か」「自分は、お金とどう付き合っていきたいか」という、自分だけの「お金の哲学」を育み始めるのです。これは、親が一方的に教えるだけでは決してたどり着けない、深い学びの領域です。
お子様の未来への最高の投資は『教育』です。専門家が監修する本格的なカリキュラムで、一生役立つお金のセンスを育みませんか?まずは詳しい資料をご覧ください。
お子様の「生きる力」を育む、はじめの一歩 Q&A

「うちの子にも、そんな本格的なマネー教育を受けさせてあげたい」。そう思っていただけたなら、とても嬉しく思います。最後に、導入を検討されている保護者様が抱くであろう疑問に、一つひとつ丁寧にお答えします。お子様の未来を豊かにする「生きる力」を育む、はじめの一歩を安心して踏み出してください。
Q1. うちの子は、まだお金に興味がないのですが…
A1. ご心配いりません。Web学童のマネー教育プログラムは、お金に興味がないお子様でも、自然と引き込まれるように設計されています。例えば、難しい座学から入るのではなく、「どうすればもっと面白い商品が作れるかな?」といった、子どもたちが大好きな「遊び」や「創造」の要素からスタートします。その中で、気づいたらお金の計算や利益の概念に触れている。そんな「学びを遊びに変える」工夫が満載ですので、どんなお子様でも楽しく参加できるはずです。
Q2. 親が金融に詳しくなくても大丈夫ですか?
A2. もちろんです。ご家庭では、日々のおこづかいなどを通じて基本的な金銭感覚を育んでいただき、社会の仕組みや資産形成といった専門的な部分は「Web学童」が担う、という役割分担が可能です。親御様が金融に詳しくなくても、お子様が体系的に学ぶ機会を提供できるのが、私たちの強みです。
また、定期的に、保護者様向けのオンライン勉強会を開催し、お子様がどんなことを学んでいるのか共有したり、ご家庭での金融教育に関するお悩みにFPがお答えしたりする機会も設けています。親子で一緒に学んでいけるのも、Web学童の魅力の一つです。
Q3. まずは何から始めれば良いですか?
A3. 今すぐお申し込みいただく必要はありません。まずは、Web学童のマネー教育がどんなものか、気軽に覗きに来てみませんか?お子様と一緒に参加できる、ハードルの低い入り口をご用意しています。
- まずは体験してみたい方 → 【無料オンラインイベント】
「おみせやさんごっこ」や「お金のクイズ大会」など、マネー教育の楽しさを親子で体験できるイベントを随時開催しています。まずは遊びに来る感覚でご参加ください。 - じっくり話を聞きたい方 → 【無料個別相談会】
「うちの子の金銭感覚、大丈夫?」「家庭での教え方、これで合ってる?」といった個別のお悩みに、専門のカウンセラーがお答えします。
お金の知識は、これからの時代をお子様がたくましく生き抜くための「武器」であり「お守り」になります。最高の贈り物を、今から一緒に準備しませんか。
>>無料オンライン説明会に申し込む
>>まずは資料を見てみる