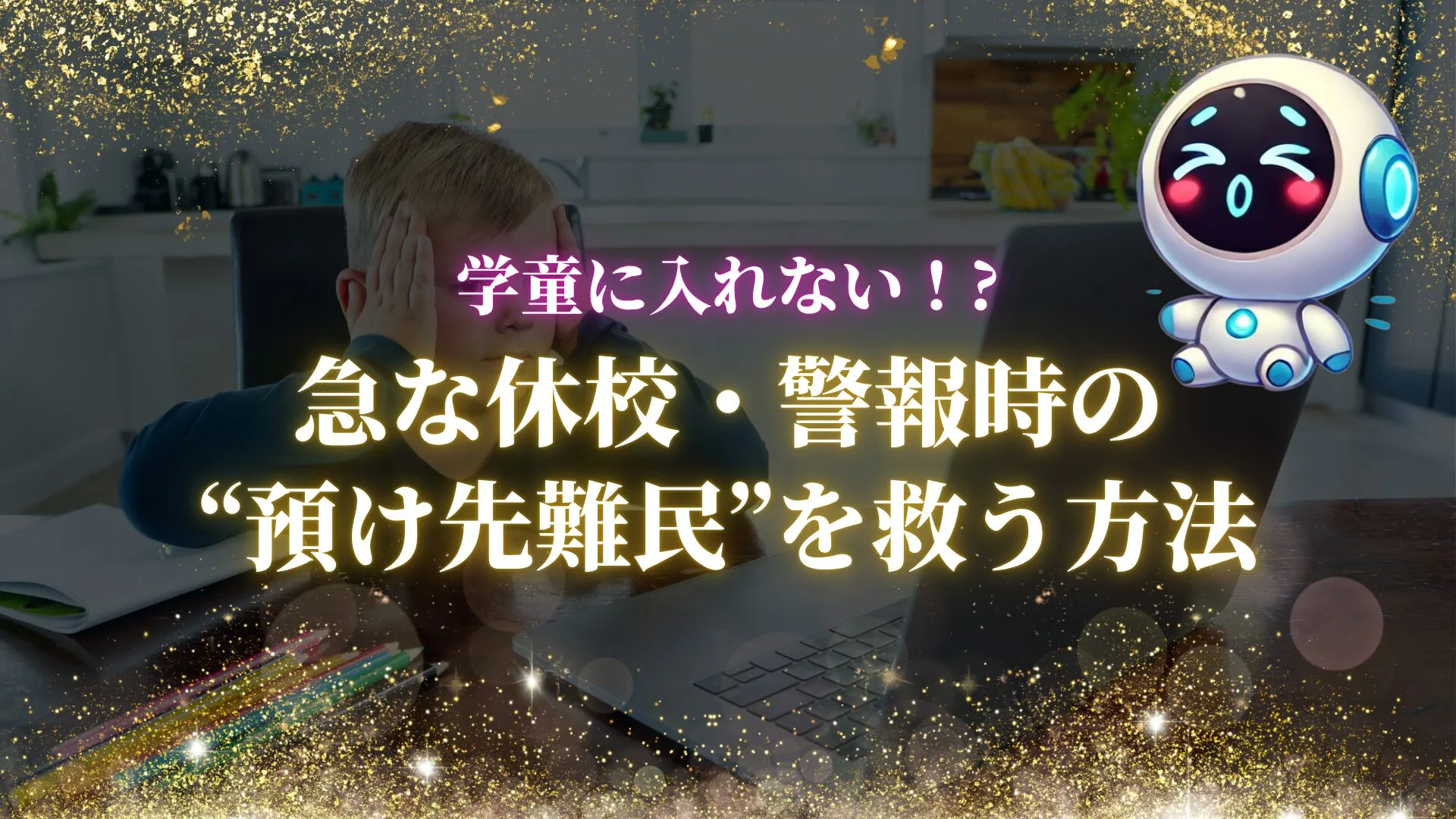「明日から学級閉鎖です」…その一本の電話で、困った経験ありませんか?

「保護者の皆様へ。明日より、お子様のクラスは学級閉鎖となります」。学校からの一斉送信メール、あるいは職場にかかってきた一本の電話。その短い文章や言葉を目にした瞬間、サーッと血の気が引いて、頭が真っ白になる…。そんな経験、共働きのご家庭なら一度や二度ではないかもしれません。
「どうしよう、明日の会議は絶対に休めない」「また仕事を調整しなくちゃいけないなんて、職場に申し訳ない…」「実家の親にお願いする?でも、この前頼んだばかりだし、気兼ねしてしまう」。
頭の中を駆け巡るのは、仕事の調整、周囲への根回し、そして何より「子どもを一人で家に置いておいて大丈夫だろうか」という、胸を締め付けられるような罪悪感と不安。
これは、学級閉鎖や台風などによる臨時休校だけの話ではありません。春先になると届く、学童の「落選通知」。その一枚の紙を見て、「これから先の1年間、どうやって乗り切ればいいの…」と目の前が真っ暗になった方もいらっしゃるでしょう。
実際に、「学童に落ちて、必死で民間の学童を探しましたが、どこも高額で定員いっぱい。パートの時間を減らすしかなく、世帯収入が大きく減ってしまいました」といった声も聞かれます。そのお悩み、そしてその時の絶望的な気持ち、痛いほどわかります。あなただけではありません。今、日本中の働く親たちが、この「小学生の預け先問題」という、見えざる大きな壁に直面し、静かな悲鳴を上げているのです。
もはや他人事ではない。「小学生の預け先難民」が急増する社会的な背景

「うちの地域は待機児童も少ないし、大丈夫だろう」。そう思っている方も、どうか他人事だと思わないでください。今、小学生の子どもを持つ共働き家庭の「預け先問題」は、個人の努力だけではどうにもならない、社会構造的な問題へと変化しています。そして、その背景には、決して無視できないいくつかの要因が絡み合っています。
この問題に直面したとき、「私の働き方が悪いのかな」「もっとうまく立ち回るべきだった…」とご自身を責めてしまうかもしれません。しかし、それは違います。これは、あなたのせいでは決してないのです。
ケース①:学童の抽選に落ちた・定員オーバー
「学童は低学年なら入れる」と考えられてきましたが、地域によってはその常識が通用しなくなりつつあります。女性の就業率向上に伴い、放課後児童クラブ(学童)の利用希望者は年々増加。特に東京、大阪、福岡などの都市部を中心に、定員を大幅に超える申し込みが殺到し、小学1年生ですら入れない「待機児童」が社会問題化しています。
こども家庭庁の「令和5年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」によると、待機児童数は16,276人(2023年5月1日時点)にのぼり、依然として多くの家庭が望んでも利用できないという厳しい現実があります。
ケース②:小4の壁で、放課後の居場所がなくなった
たとえ低学年の間は学童に入れたとしても、次に待ち受けるのが「小4の壁」です。多くの公設学童は、定員の都合上、小学校3年生までしか利用できないケースが多く、4年生になると突然、放課後の居場所を失ってしまうのです。子どもは少し大きくなったとはいえ、毎日何時間も一人で留守番させるのは、防犯面でも安全面でもやはり不安がつきまといます。「鍵はちゃんと閉めたかな」「火の元は大丈夫かな」「寂しい思いをしていないかな」。仕事中も、そんな心配が頭から離れない、という親御さんは少なくありません。
ケース③:学級閉鎖・警報など、突発的な休校
そして、最も対応が難しく、保護者に重くのしかかるのが、インフルエンザや感染症による学級閉鎖、あるいは台風や大雪警報による突発的な休校です。これは、学童に通えているかどうかに関わらず、すべてのご家庭に降りかかる問題です。
実際に、「去年はインフルエンザとコロナで、子どもが合計3回も学級閉鎖に。有給はあっという間になくなり、最後は欠勤扱いに。本当に死活問題でした」という切実な声もあります。予測不能で、ある日突然やってくる「子どもの預け先がない」という事態。公的なサポートにも限界がある今、私たち親には、万が一に備える「自衛策」を持つことが求められているのかもしれません。
どう乗り切る?既存の解決策とその”限界”

「じゃあ、実際に学童に入れなかったり、急な休校になったりしたら、みんなどうしているの?」その問いに対して、多くのご家庭が試行錯誤しながら、いくつかの選択肢を組み合わせてなんとか乗り切っているのが現状です。しかし、どの選択肢にも、メリットがある一方で、無視できない”限界”や”負担”が存在します。ここでは、代表的な解決策とその課題点を整理してみましょう。
選択肢①:仕事を休む・在宅勤務に切り替える
最も手っ取り早い方法は、親が仕事を休む、あるいは在宅勤務に切り替えることです。子どもが一人ではないという安心感は何にも代えがたいものです。しかし、その裏側で、私たちは多くのものを犠牲にしています。仕事を休めば収入が減りますし、重要な会議や取引先との約束をキャンセルすれば、キャリアに響くかもしれません。
在宅勤務に切り替えられたとしても、「ママ、見て見て!」「ねぇ、遊んで!」という子どものおねだりを横目に、オンライン会議に集中するのは至難の業。「仕事にも子どもにも集中できない」という二重のストレスを抱え、かえって心身ともに疲弊してしまう方も少なくありません。
選択肢②:祖父母・親戚に頼る
近くに頼れる祖父母や親戚がいるご家庭は、本当に心強いでしょう。気心の知れた身内に預けられる安心感は絶大です。しかし、これも万能の解決策ではありません。多くの人が、「毎回お世話になるのが申し訳なくて、すごく気を使ってしまいます。本当は少し休んでほしいだろうなと思うと、気軽に『お願い』とは言えなくて…」と感じています。祖父母の体力的な負担や、価値観の違いによる小さな衝突、そして何より「頼る側の気疲れ」は、決して小さな問題ではありません。貴重なセーフティネットだからこそ、”最後の切り札”として温存しておきたい、というのが本音ではないでしょうか。
選択肢③:ファミリーサポート・ベビーシッター
専門のサービスに頼る、という選択肢もあります。ファミリーサポートやベビーシッターは、プロに安心して預けられるという大きなメリットがあります。しかし、そのハードルは決して低くありません。まず、費用も課題です。
例えばベビーシッターの場合、地域や事業者にもよりますが1時間あたり2,000円〜3,000円が相場と言われることもあり、一日預ければ1万円を超える出費になるケースも珍しくありません。これが何日も続けば、家計へのダメージは計り知れません。また、多くのサービスは事前の登録や面談が必要で、「明日、急に!」というニーズには応えにくいのが実情です。運よくマッチングできても、「知らない人を家に上げるのは少し抵抗がある」と感じる方もいるでしょう。
これらの選択肢は、どれも一長一短。私たちは、その場その場でなんとかパッチワークのように組み合わせて危機を乗り越えていますが、心のどこかで「もっと根本的で、安心できる解決策はないものか…」と感じているはずです。
既存の対策ではもう限界…と感じていませんか?費用や手間をかけずに、親も子も安心できる“新しい選択肢”があります。
>>自宅が安全な預け先になる「Web学童」とは?
第3の選択肢。「Web学童」という新しい備え

仕事を休む罪悪感、祖父母への気兼ね、シッターに頼む費用と手間…。既存の解決策が持つ課題を補い、新たな選択肢となるのが、私たちの提案する**「Web学童」**です。
「Web学童」と聞くと、単なるオンラインの習い事をイメージされるかもしれません。しかし、その本質は「自宅を、最も安全で、学びのある預け先に変える」という、預け先問題に対する革新的なソリューションにあります。これまであなたが抱えてきた悩みに寄り添う「第3の選択肢」。その具体的なメリットをご紹介します。
【安心】自宅だから安全。親は仕事に集中できる
Web学童の最大のメリットは、「自宅で完結する」という点です。学童への行き帰りに、交通事故に遭わないか、不審者に声をかけられないか…。そんな心配は一切ありません。インフルエンザや感染症が流行している時期でも、外部からの感染リスクを大幅に低減できます。 お子様は最も慣れ親しんだ安全な空間で過ごし、親は仕事場や在宅ワークで、安心して自分の業務に集中することができます。サービスによっては、お子様のログイン状況が保護者に通知されたり、オンライン上のスタッフが常に見守ってくれたりする機能もあり、「一人で留守番」させているという罪悪感からも解放されます。
【学び】ただの留守番じゃない。「学習の遅れ」も防げる
急な休校で一番心配なのが「学習の遅れ」です。Web学童は、ただ子どもを画面の前に座らせておくだけの「オンライン託児所」ではありません。お子様がいつでも利用できる「習い事」という側面があります。
例えば、国語や算数などの基礎学習はもちろん、プログラミングや探求学習といった、知的好奇心を引き出す多彩な学びの時間が用意されています。ご利用者様からは、「学級閉鎖中、ただYouTubeを見せて過ごさせることに罪悪感がありましたが、Web学童のおかげで、むしろ普段より集中して勉強していました。復帰後の授業にもスムーズについていけたようです」といった声をいただいています。(※個人の感想です)
退屈な留守番を、有意義な学びに変えられる。これは、他の解決策にはない、Web学童ならではの大きな価値です。
【即応性】緊急時こそ真価を発揮。登録しておくだけで”お守り”に
「明日から学級閉鎖です」。その連絡が来た瞬間に、真価を発揮するのがWeb学童です。シッターのように慌てて人を探す必要も、仕事を調整する必要もありません。インターネット環境とPC・タブレットさえあれば、翌日の朝からすぐにお子様を「オンラインの居場所」に参加させることができます。月々決まった料金で、この「いざという時の安心」を手に入れられる。これは、まさに共働き家庭にとっての「保険」であり「お守り」のような存在です。普段は放課後の学習習慣づくりのために利用し、緊急時には朝からの預け先として活用する。そんな柔軟な使い方ができるのも、Web学童の大きな魅力です。
「明日どうしよう…」という不安から解放されませんか?いざという時の“お守り”として、多くのご家庭が選んでいます。まずは詳しい資料で、安心の仕組みをご確認ください。
>>【無料】資料請求で「いざという時の備え」をする
「Web学童」利用者の声から見る、リアルな変化

「Web学童が便利なのはわかったけれど、実際に使っている人はどう感じているの?」そんな疑問にお答えするために、ここでは実際に「Web学童」を利用して、預け先の悩みから解放されたご家庭のリアルな声をご紹介します。あなたと同じ悩みを抱えていた方々のストーリーに、きっと共感していただけるはずです。
ケース①:学童の抽選に落ち、途方に暮れていたKさん親子(東京都在住・小1)
※これは利用者の声を元に再構成した個人の体験談です。
「第一子で、フルタイム勤務。学童に入れなかった時は、本当に目の前が真っ暗になりました。仕事を辞めるしかないのかと追い詰められていた時に、Web学童を知りました。最初はオンラインで大丈夫かと半信半疑でしたが、体験会に参加した息子が『楽しい!明日もやりたい!』と言ってくれたのが決め手でした。今では、学校から帰ると自分でPCを立ち上げてログインするのが日課です。学習プログラムだけでなく、全国の友達とオンラインでクイズをしたり、おしゃべりしたりする時間が何より楽しいようです。私が仕事を終えて帰宅すると、『今日はこんなことを学んだよ!』と目を輝かせて報告してくれます。」
ケース②:急な学級閉鎖で、Web学童に救われたFさん(大阪府在住・小3)
※これは利用者の声を元に再構成した個人の体験談です。
「インフルエンザで突然の学級閉鎖。夫婦ともにどうしても休めない仕事があり、まさにパニック状態でした。そんな時、以前から”お守り”のつもりで登録していたWeb学童のことを思い出したんです。ダメ元で朝から参加させてみると、専門のスタッフさんが『Fくん、おはよう!今日はお家で一緒に頑張ろうね!』と温かく迎えてくれて…。息子は寂しがるどころか、『オンラインの学校みたいで楽しい!』と大喜び。私は安心して仕事に集中でき、本当に助かりました。以来、我が家にとってWeb学童はなくてはならない存在です」
これらの声は、決して特別なものではありません。「Web学童」は、全国で「預け先難民」となり、孤立しがちなご家庭にとって、確かな安心と繋がりを提供しています。
今すぐできる、不安への備え。Web学童に関するQ&A

「うちも、いざという時のために入っておこうかな…」。そう考えてくださった方のために、最後の疑問や不安を解消するQ&Aコーナーをご用意しました。安心して、不安への備えの第一歩を踏み出してください。
Q1. 月々の料金は?シッターを頼むよりお得?
A1. サービス内容は異なりますが、コスト面で比較すると、例えばベビーシッターを月に1〜2日頼む費用で、Web学童の月額プラン(平日毎日利用可能など)をご利用いただけるケースもございます。日々の学習サポートに加え、緊急時の保険としての役割も考えると、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢の一つと言えます。
Q2. 子どもが一人でPCやタブレットを操作できますか?
A2. ご安心ください。最初の数回、ログイン方法などを一緒に確認していただければ、あとはお子様一人で参加できるケースがほとんどです。また、操作で困ったことがあれば、オンライン上に常に待機しているスタッフがすぐにサポートしますので、IT機器に不慣れなご家庭でもスムーズにご利用いただけます。
Q3. まずは何から始めればいいですか?
A3. 「備えあれば憂いなし」です。ぜひ、”何も起きていない平穏な今”だからこそ、情報収集から始めてみてください。いきなり申し込む必要はありません。無理な勧誘も一切ございませんので、ご安心ください。
- まずはじっくり知りたい方 →【無料資料請求】
サービス内容、料金プラン、緊急時の利用方法などを詳しく解説した資料をお送りします。「いざという時」に備えて、ファイルに挟んでおくだけでも安心感が違います。 - 気軽に相談してみたい方 →【オンライン無料個別相談】
「うちの家庭環境に合う?」「こういう時はどう使える?」といった具体的な疑問に、専門のカウンセラーがオンラインでお答えします。あなたのご家庭だけの使い方を一緒に考えます。
もう、子どもの預け先のことで、一人で悩み、頭を抱えるのは終わりにしませんか。安心というお守りを手に入れて、心穏やかな毎日を送りましょう。
>>【オンラインで完結】無料個別相談に申し込む
>>まずは資料を見てみる