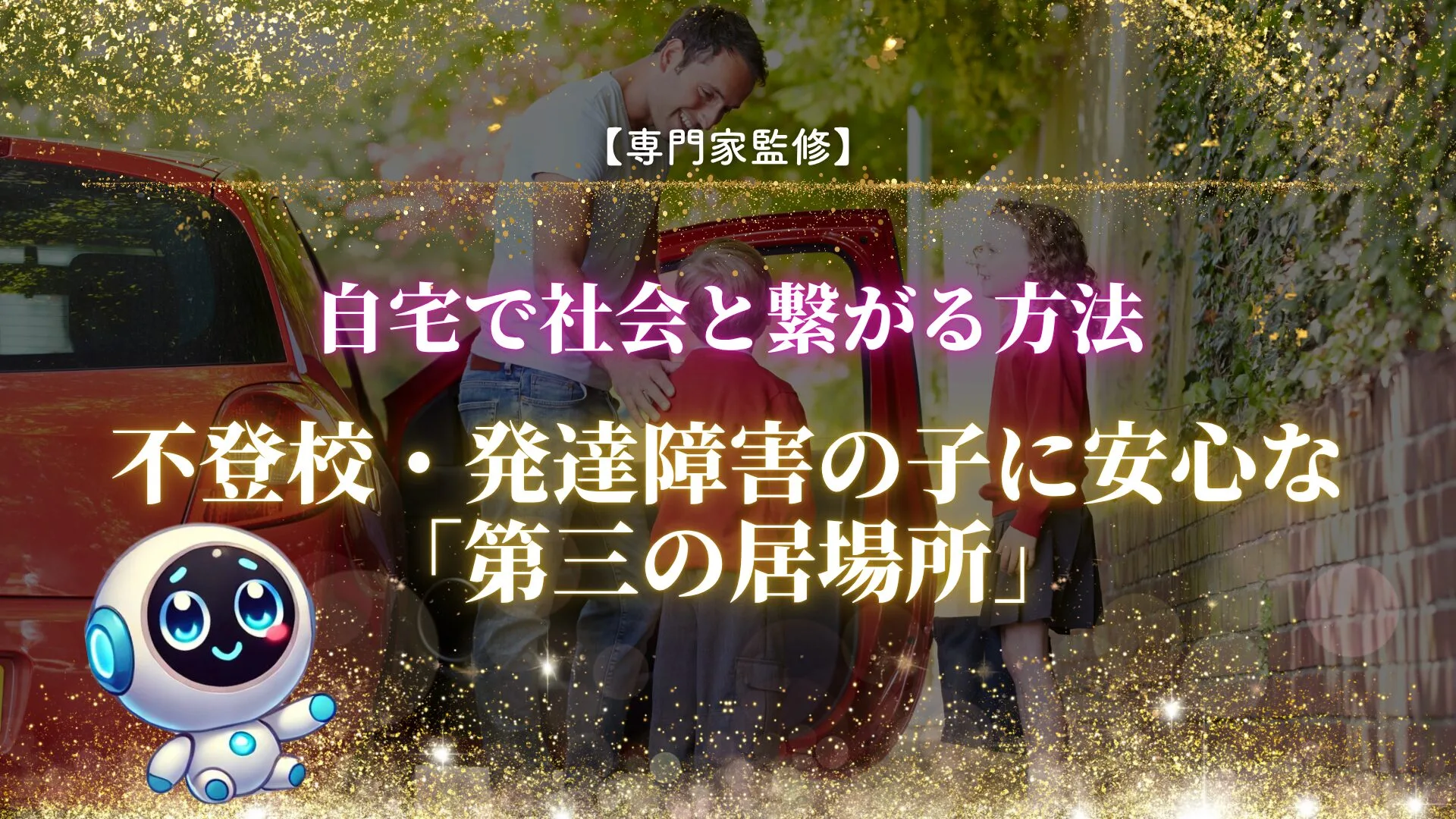「出口のないトンネルにいるよう…」― お子様の不登校、一人で抱え込んでいませんか?

「学校、行きたくない…」
朝、布団から出てこない我が子の背中を見つめながら、「今日もか…」と、重たい気持ちになっていないでしょうか。
先の見えない毎日と日に日に失われていく子どもの笑顔。そして、「この子の将来は、一体どうなってしまうのだろう」という、底なし沼のような不安。
誰にも相談できない。「育て方が悪かったのでは」と自分を責める夜。「学校に行かないなんて、甘えているだけだ」という世間の無理解な声に、心がすり減っていく。
もし、あなたが今、そんな出口のない暗いトンネルの中にいるように感じているのなら。どうか、これだけは信じてください。あなたも、あなたのお子様も、決して一人ではありません。
文部科学省「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等調査」によると、小・中学校における不登校児童生徒数は過去最多の299,048人にのぼります。これは、決して他人事ではない、すぐ隣にある現実です。そして、その背景には、お子様が持つ繊細な「特性」が隠れていることが少なくありません。
その孤独感、焦り、そして罪悪感。痛いほど、わかります。でも、もう一人で抱え込む必要はないのです。
なぜ学校に行きづらい?発達特性と「エネルギー切れ」の関係

お子様が学校に行けなくなった時、多くの親御さんは「私の育て方が悪かったのか」「本人の気持ちが弱いからだ」と、原因を自分や子どもに求めてしまいます。しかし、不登校の背景を考えるとき、その原因を本人の怠惰や親の育て方に求めるのは、適切なアプローチではありません。
特に、発達障害(診断済み・あるいは診断はないものの特性が見られる「グレーゾーン」※)の特性を持つお子様にとって、今の日本の学校は、心身のエネルギーを過剰に消耗してしまう場所になり得ます。
(※「グレーゾーン」は医学的な診断名ではなく、発達障害の特性が見られるものの、診断基準をすべて満たすわけではない状態を指す一般的な表現です。)
あなたのスマートフォンを想像してみてください。たくさんのアプリを同時に立ち上げ、常にWi-FiやBluetoothで外部と通信し、画面の明るさも最大にしていると、バッテリーはあっという間になくなりますよね。
発達特性を持つお子様の脳は、まさにこの状態に近いのです。
- 周りのざわめきや蛍光灯の光、給食の匂いなど、五感から入る刺激を人一倍強く感じ取ってしまう。
- 友達の表情や先生の声のトーンから、相手の気持ちを深読みしすぎて疲れてしまう。
- 「きちんと座っていなければ」「忘れ物をしてはいけない」など、目に見えないルールに必死に適応しようと、常に頭をフル回転させている。
マジョリティ(多数派)の子どもたちが無意識にできることを、彼らは一つひとつ、膨大なエネルギーを使ってこなしています。その結果、心と体のバッテリーが完全に尽きてしまい、「エネルギー切れ」を起こしてしまうのです。
朝、起きられない。学校に行こうとすると、お腹が痛くなったり、頭が痛くなったりする。これは、怠けているのではなく、「これ以上エネルギーを使ったら、心身が壊れてしまう」という、体からの悲鳴であり、自己防衛反応なのです。
まず、お子様を休ませてあげること。そして、「学校に行けないのは、あなたが一日頑張りすぎた証拠なんだよ」と、その子の苦しみを理解し、肯定してあげることが、回復への何より大切な第一歩となります。
在宅学習のジレンマ。「学び」はできても「繋がり」が生まれない

お子様が学校を休み始めると、保護者の方が次に直面するのが、「学習の遅れ」と「社会的な孤立」という2つの大きな不安です。
「このままでは、勉強がどんどん遅れてしまう…」。その不安を解消するために、通信教育を始めたり、学習アプリを試したり、あるいは親御さん自身が先生役となってドリルを教えたり、様々な工夫をされていることでしょう。自宅という安心できる環境で、その子のペースに合わせて学習を進める。それは、エネルギーを回復させる上で非常に有効な手段です。
しかし、在宅での学習は、「学びの遅れ」には対応できても、「社会との繋がり」という、人間が成長する上で不可欠な要素をどう補うか、という新たな課題を生みます。一日中親子だけで過ごす中で、「このまま同世代の子と関わらないままで、社会性は育つのだろうか」という不安を抱くのは、当然のことです。
この状況は、お子様の孤立感を深めるだけでなく、すべての役割を一人で担わなければならない親御さんの負担と孤独をも、増大させてしまうのです。学びの保証と、社会との繋がり。この2つを、エネルギーの少ないお子様が、自宅という安全基地にいながら両立できる方法はないのでしょうか。
学習の遅れと、社会的な孤立。この2つの不安を、自宅にいながら同時に解消できるとしたら…?
>>オンライン上の「第三の居場所」について知る
自宅が安心の「サードプレイス」になる、オンライン学童

学校(セカンドプレイス)にも行けず、家庭(ファーストプレイス)に閉じこもりがちになっているお子様にとって、今、最も必要なもの。それは、心から安心でき、ありのままの自分でいられる「第三の居場所(サードプレイス)」です。
フリースクールや地域の適応指導教室は、専門的な支援を受けられる素晴らしい選択肢です。しかし、エネルギーが枯渇しているお子様にとっては、まず「家から出る」ということ自体が非常に高いハードルになる場合があります。
そこで、私たちが提案するのが、「物理的な移動が一切不要」な、オンライン上のサードプレイス、「Web学童」です。自宅の自分の部屋から、ワンクリックで繋がれる社会との接点。これこそが、不登校や発達障害で悩むお子様と、そのご家族にとって、現実的な第一歩となりうる、希望に満ちた新しい選択肢の一つです。
①孤立からの脱却:「共通の好き」で繋がる、心理的安全性の高いコミュニティ
学校のクラスは、興味も性格もバラバラな子どもたちが、偶然集められた強制的な集団です。しかし、Web学童のコミュニティは違います。「マインクラフトが好き」「絵を描くのが好き」「歴史の謎について語りたい」といった、「共通の好き」という旗印のもとに、全国から仲間が集まります。 好きなものが同じだから、自然と会話が生まれる。お互いの知識や作品を尊敬し合える。
そこには、学校のような同調圧力や、無理に自分を偽る必要はありません。チャットでの参加や、カメラオフで聞くだけの参加も、もちろんOK。「自分に合った方法で、輪の中にいていいんだ」という経験は、失いかけた他者への信頼感を、少しずつ取り戻させてくれます。
②自己肯定感の回復:スモールステップで「できた!」を積み重ねる
学校という集団の中では、「できないこと」ばかりに目が向きがちです。しかし、Web学童では、専門のメンター(講師)が、その子の「できたこと」「挑戦したこと」を丁寧に見つけ、承認します。
「今日は、勇気を出してチャットで一言発言できたね。すごいよ!」
「〇〇くんが作ったマインクラフトの細部へのこだわりが素晴らしいね」
集団の中の一人としてではなく、価値ある「個」として尊重される経験。この小さな成功体験(スモールステップ)の積み重ねが、「自分も、まんざらじゃないかも」「これならできるかも」という、自己肯定感の芽を、ゆっくりと、しかし確実に育てていくのです。
③未来に繋がる自立支援:”好き”を”自信”に変える学び
不登校のお子様は、有り余る時間の中で、自分の好きなことに驚異的な集中力を発揮することがあります。Web学童は、その「好き」や「得意」を、学びに、そして将来の自信に変える場所です。例えば、ゲームが好きなら、プログラミングを学んで自分でゲームを作ってみる。絵を描くのが好きなら、デジタルアートのツールを学んで、世界に発信してみる。学校の画一的なカリキュラムに縛られず、自分の探求したいことを、専門家のサポートを受けながらトコトン深掘りできる。この経験は、「自分にはこれがある」という揺るぎない自信となり、社会的な自立への、大きな一歩となる可能性を秘めているのです。
お子様が本来持っている好奇心や笑顔を取り戻すために。私たちがどのようなサポートで寄り添えるのか、詳しい資料でご確認ください。お子様の可能性を、私たちは信じています。
>>【無料】資料請求で安心のサポート体制を確認する
「うちの子にはまだ早いかも…」導入前によくあるご質問

「自宅から繋がれるのは、すごく魅力的。でも、うちの子は人と関わること自体に強い不安があるから、オンラインでも難しいかもしれない…」。そのように、一歩踏み出すことを躊躇してしまうお気持ち、お察しします。最も慎重にならなければいけない時期だからこそ、その懸念に、一つひとつ丁寧にお答えさせてください。
Q1. パソコンの操作も苦手で、対人不安が強い子でも参加できますか?
A1. はい、ご安心ください。私たちは、そのようなお子様を数多くサポートしてきた実績があります。Web学童では、お子様の状態に合わせて、参加の形を柔軟に変えることができます。例えば、保護者様と一緒にプログラムを見学することから始められます。慣れてきたら、お子様自身のアカウントで、カメラもマイクもオフにしたまま「見るだけ・聞くだけ」で参加する。
そして、メンター(講師)が個別のチャットで「〇〇くん、見てくれてるんだね。ありがとう」と、そっと声をかける。このように、焦らず、お子様のペースで、0.1歩ずつ進んでいく手厚いサポート体制を整えています。対人不安の強いお子様にとって、非常にハードルの低い「社会参加の入り口」の一つになれると考えています。
Q2. 親はどの程度、関わる必要がありますか?
A2. 親御さんが常に付きっきりでいる必要は全くありません。むしろ、お子様が自立して参加できるようになることが、私たちの目標の一つです。しかし、その一方で、私たちは保護者様との連携を非常に大切にしています。 メンター(講師)は、日々のセッションでのお子様の様子(「今日はチャットでこんな発言がありましたよ」「〇〇という分野に興味を示していました」など)を、連絡帳のような形で保護者様と共有します。
これにより、保護者様は家庭では見られないお子様の成長を知ることができます。これは、「親の孤立」を解消することにも繋がります。お子様のこと、そしてご自身のことを、何でも話せる「伴走者」として、私たちを頼ってください。
>>【保護者様だけでもOK】無料オンライン個別相談に申し込む