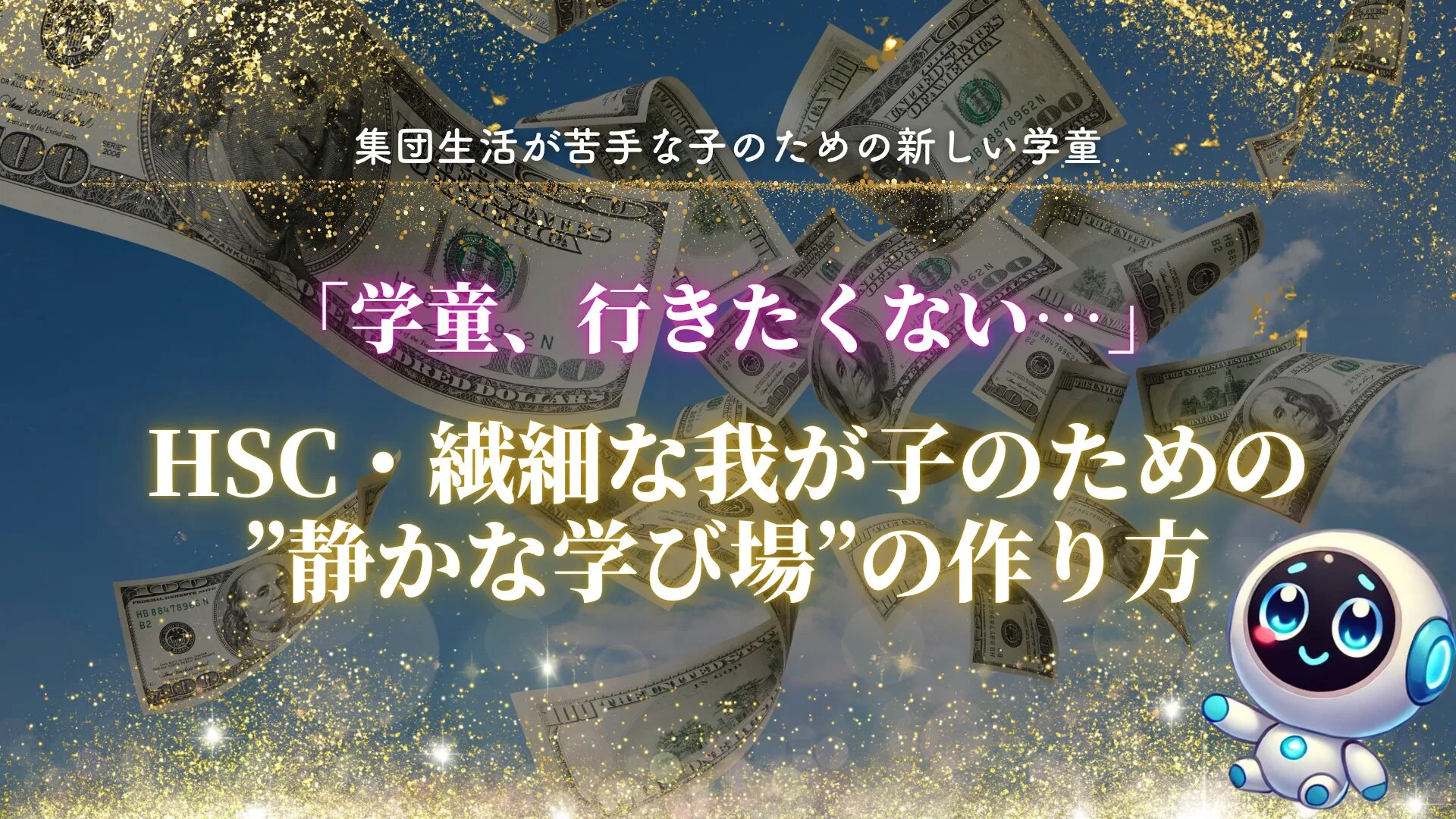「学校から帰ると、元気がない…」集団が苦手な子が発するSOSサイン

学校から帰ってくるなり、玄関にランドセルを放り投げて、どっとソファに倒れ込む。話しかけても、上の空。大好きだったはずのゲームにも、YouTubeにも興味を示さず、ただただ、魂が抜けたようにぐったりしている…。
また、朝になると「お腹が痛い」「頭が痛い」と言い出し、学校や学童に行きたがらない。友達との些細なやり取りをいつまでも気にして泣き出す。
お子様のそんな姿に「どうしてうちの子だけ…」「私がもっと強く育てていれば…」と、出口の見えない暗いトンネルの中で、ご自身を責めてしまっているかもしれません。
そのお悩み、そして、誰にも理解されない孤独感、本当にお辛いことと思います。ですが、どうかこれだけは知ってください。そのお悩みは、決してあなただけのものではありません。 全国には、あなたと全く同じように心を痛めている仲間が、たくさんいるのです。そして何より、それはお子様の「わがまま」でも、あなたの「育て方のせい」でも、決してないということを。それは、お子様が発している、切実な「SOSサイン」なのです。
それは「欠点」ではなく「個性」。集団が苦手な子の繊細な心の内側
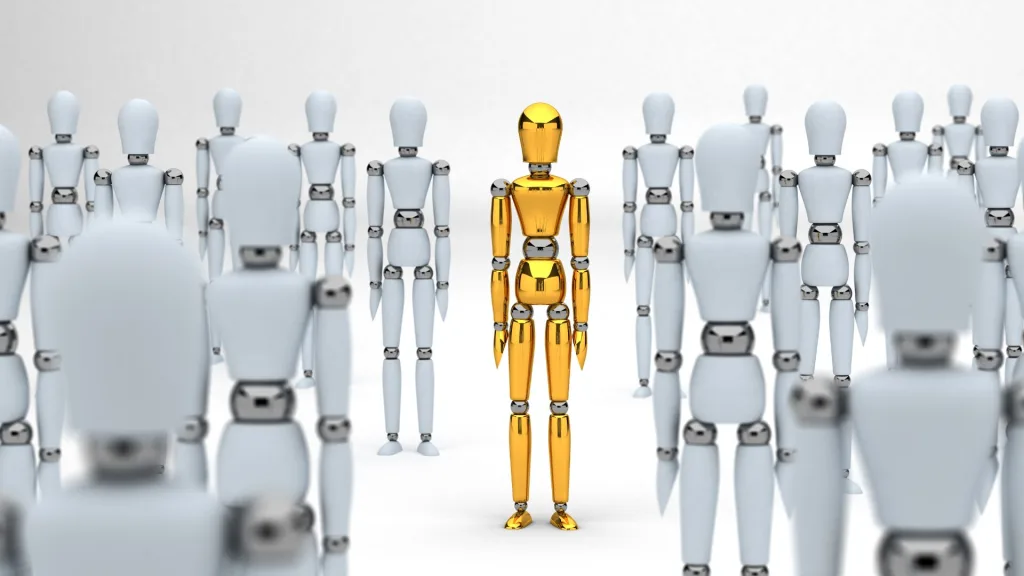
「集団行動が苦手」と聞くと、私たちはつい「協調性がない」「社会性に問題がある」といったネガティブなレッテルを貼ってしまいがちです。しかし、心理学的な観点から見ると、それは全くの誤解です。集団が苦手という特性は、「欠点」などではなく、その子だけが持つ、かけがえのない「個性」なのです。
集団が苦手な背景には、様々な個性があります。例えば、米国の心理学者エレイン・アーロン博士が提唱したHSC(ひといちばい敏感な子)という概念があります。これは病気や障害ではなく、生まれ持った「気質」の一つで、周りの刺激を深く処理し、共感性が高いといった特性があります。
また、発達障害の診断基準は満たさないものの、コミュニケーションや集中力などに特性の凹凸が見られる「グレーゾーン」と呼ばれるお子様もいます。これらの多様な個性を持つ子どもたちは、多くの子ども達とは異なる感じ方をしているため、集団生活で人一倍エネルギーを消耗することがあります。
なぜ、普通の学童だと疲れてしまうのか?
これを踏まえて、一般的な学童の環境を思い浮かべてみてください。何十人もの子どもたちの騒ぎ声、蛍光灯の強い光、あちこちで始まるドッジボール、常に誰かの視線にさらされている感覚…。多くの子にとっては「活気があって楽しい場所」でも、集団が苦手な子にとっては、あらゆる刺激が飽和した、嵐のような空間に感じられます。
彼らは、その嵐の中で、必死にエネルギーを使い、周りの子と同じように「普通」に振る舞おうと頑張っています。予測不能な友達の動きに常にアンテナを張り、暗黙のルールを読み取ろうと必死で頭を働かせています。だから、家に帰る頃には、心も体もエネルギー切れでぐったりしてしまうのです。
「学童不適応」は、お子様自身に問題があるのではなく、その子の繊細な心と、学童という環境とのミスマッチが大きな要因となっているケースがほとんどです。大切なのは、その子の「個性」を丸ごと認め、「あなたはあなたのままで100点満点なんだよ」と伝えてあげることです。
選択肢は「無理に慣れさせる」だけじゃない。その子に合った環境を選ぶ時代へ

「集団が苦手なのは分かった。でも、この先ずっと集団生活から逃げるわけにはいかない。なんとか無理にでも慣れさせなければ…」。そう考えるお気持ちも、痛いほどわかります。社会で生きていくためには、ある程度の適応力も必要だ、と考えるのは当然のことです。
しかし、考えてみてください。サイズの合わない靴を無理に履き続けたら、足は傷だらけになり、歩くこと自体が苦痛になりますよね。それと同じで、その子の心に合わない環境に無理やり押し込み続けることは、自信を失わせ、「自分はダメな人間なんだ」という深い自己否定感を植え付けてしまう危険性があるのです。
今は、多様性が尊重される時代です。選択肢は「無理に慣れさせる」だけではありません。幸い、学童の代替となる選択肢も増えてきました。例えば、少人数制の民間学童はアットホームな魅力がありますが、都市部に集中しがちで費用も高額になる傾向があります。
また、習い事や家庭教師は特定のスキルを伸ばせますが、同世代との幅広い交流機会は得にくいかもしれません。お住まいの地域やご家庭の状況によって、選択肢が限られてしまうのが大きな課題です。
もっと根本的に、その子のペースと安心感を何よりも尊重できる、新しい解決策はないのでしょうか。
お子様に合った環境が、なかなか見つからない…そう感じていませんか?自宅という最高の”安全基地”から、その子のペースで社会と繋がれる新しい選択肢があります。
>>集団が苦手な子のための「オンライン学童」とは?
答えは、自宅という”安全基地”から学ぶ「オンライン学童」

「集団の騒がしさは苦手。でも、一人ぼっちは寂しい」「学びたい気持ちはある。でも、自分のペースでやりたい」。
そんな、集団が苦手な子の繊細で複雑な願いを、すべて叶えることができる場所。それが、私たちの提案する「オンライン学童(Web学童)」です。Web学童は、これまでの「どこかの場所に通う」という常識を覆し、自宅という最高の”安全基地”を、そのまま学びと交流の場に変える、新しい選択肢です。
特に、お子様が「静かに学べる学童」を探しているなら、非常に有力な選択肢の一つとなるでしょう。Web学童は、集団生活のデメリットである「過剰な刺激」や「同調圧力」を限りなくゼロにし、メリットである「学びの機会」や「質の高い交流」だけを、その子に最適な形で提供できるように、徹底的に「個別最適化」されています。
①環境の個別最適化:自分の部屋が、刺激の少ない最高の学び場になる
Web学童では、お子様の学習机が、そのまま教室の最前列になります。あなたが工夫して整えた、刺激の少ない静かな環境で、誰にも邪魔されずにプログラムに参加できます。周りの子の視線も、突然の大きな物音もありません。もし疲れたら、誰に気兼ねすることなく、そっとカメラをオフにしたり、ヘッドホンで耳を休ませたりすることも自由です。
この「自分で自分の環境をコントロールできる」という感覚は、受け身になりがちだったお子様に、「自分で選んでいる」という主体性と自信を与えてくれます。
②コミュニケーションの個別最適化:話すのが苦手でも「チャット」で参加できる
大勢の前で発言するのが苦手なお子様はたくさんいます。しかし、話すのは苦手でも、文章でなら、自分の考えをじっくりまとめて表現できる、という子も少なくありません。Web学童では、マイクで話すだけでなく、「チャット機能」を使ってテキストで意見を表明することも、立派な参加方法として認められています。「うちの子は、人前で話すのが大の苦手でしたが、Web学童のチャットで自分の意見をたくさん書き込んでいるのを見て、こんな一面があったのかと驚きました」といった声も聞かれます。自分に合った方法で輪に入れる、という成功体験は、コミュニケーションへの苦手意識を少しずつ溶かしてくれます。
③サポートの個別最適化:特性を理解した専門メンターが、その子の「良い所」を引き出す
Web学童のメンター(講師)の中には、HSCや発達特性に関する専門的な研修を受け、一人ひとりの個性を深く理解した方も在籍しています。メンターは、集団の中の一人としてではなく、「大切なあなた」として、お子様一人ひとりの様子を丁寧に見守ります。
そして、「〇〇さんの、この独特な視点はすごいね」「〇〇くんの集中力は、本当に素晴らしい才能だよ」と、その子の「良い所」「強み」を見つけ出し、具体的に言葉にして伝えます。学校や集団の中では見過ごされがちだった長所を、信頼できる大人に認められる経験は、傷つきがちだったお子様の自己肯定感を、根っこから育て直してくれるでしょう。
お子様の素晴らしい個性を、私たちは全力で肯定します。その子の”好き”や”得意”が輝く場所が、ここにあります。まずは詳しい資料で、私たちの想いとサポート体制をご覧ください。
>>【無料】資料請求でサポート体制の詳細を見る
「うちの子でも大丈夫?」導入前に解消したい3つの不安

「集団が苦手なうちの子にとって、まさに理想の場所かもしれない…。でも、本当にうちの子でも大丈夫かしら」。そのように、期待と同時に、慎重に考えてしまうお気持ち、とてもよく分かります。繊細なお子様を持つ保護者様だからこそ、新しい環境に一歩踏み出すのは勇気がいることですよね。ここでは、そんなあなたの最後の不安に、一つひとつお答えします。
Q1. 人見知りが激しく、オンラインでも固まってしまいそうで心配です…
A1. そのご心配は、本当によく分かります。ご安心ください。私たちは、お子様を無理やり輪の中に入れようとは、決してしません。Web学童では、「見るだけ」「聞くだけ」の参加も、立派な”参加”だと考えています。最初はカメラもマイクもオフにしたまま、他の子たちがどんなことをしているのか、そっと様子を眺めているだけでも大丈夫です。
メンターは、そんなお子様の存在をきちんと認識し、「〇〇さん、見てくれているんだね、ありがとう」と、その子の存在を肯定する声かけをします。焦らず、急かさず、お子様のペースで、少しずつ氷を溶かしていく。そんな丁寧なサポート体制が整っているので、ご安心ください。
Q2. 他の子とのリアルな関わりが減ってしまうのでは?
A2. 「社会性」についてのご心配ですね。実は、私たちは「リアルな関わりの量」よりも「コミュニケーションの質」の方が、社会性を育む上で重要だと考えています。学校の教室で、ただ周りに合わせて黙って座っている1時間と、オンライン上で、共通の好きなことについて、国や地域を超えた仲間と夢中になって語り合う1時間。どちらがお子様にとって有意義な時間でしょうか。
Web学童では、後者のような、深く、質の高いコミュニケーションの機会を数多く提供しています。また、希望者が参加できるオフラインのイベント(例えば、東京や大阪、福岡などの主要都市での交流会)を企画することもあり、リアルな繋がりを育む機会も大切にしています。
Q3. まずは何から始めたら良いですか?
A3. これまで、本当にたくさんのことを調べ、悩み、一人で抱えてこられたことと思います。ですから、まずは、そのお話を私たちに聞かせてください。お子様のこと、ご家庭での様子、あなたが感じている不安、どんな些細なことでも構いません。Web学童では、サービスの説明会よりも、保護者様一人ひとりと向き合う「無料の個別相談」に最も力を入れています。
保護者様だけでご参加いただいても全く問題ありません。専門のスタッフが、あなたとお子様の気持ちに寄り添いながら、最適な道筋を一緒に探します。
あなたの悩み、そしてお子様の素晴らしい個性について、私たちにお聞かせください。専門スタッフが、オンライン個別相談でじっくりお話を伺います。
>>【保護者様だけでもOK】無料の個別相談に申し込む